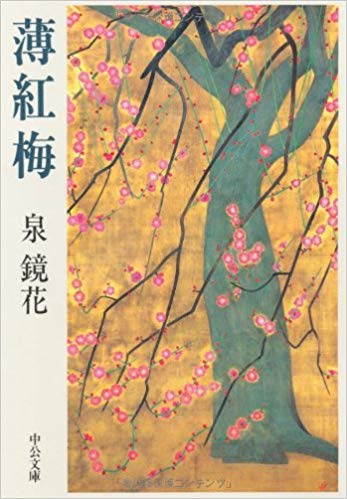「鏡花を読んでみたくて、読むたびに挫折する。でも今でも鏡花を読んでみたい」という声を聞くと、やはり考えてしまう。なぜ鏡花に挫折するのか…と。そして、それでもなぜ鏡花が読みたくなるのか…と。
◆なぜ鏡花に挫折してしまうのか その一
何といっても知らない日本語が多い。この「薄紅梅」を読むのも広辞苑では役に立たず、日本国語大辞典をひきまくった。ジャパンナレッジの会員だからタブレットで楽にひけるが、何巻もの紙の日本国語大辞典しか使えなければ、手が筋肉痛になってしまいそうである。
たとえば最後に引用している「薄紅梅 四」で大切な役割を果たしている「釣忍」である。これは広辞苑にも、日本国語大辞典にも意味がのっている。日本国語大辞典では、こう説明している。
忍草(しのぶくさ)を集めてその根をたばね、いろいろの形につくり、軒先などにつるして涼感をそえるもの。
まだまだイメージが浮かんでこない。
さらに画像を探せば、見慣れたものが出てくる。なんだ、これを釣忍と言うのか! 鏡花の時代には当たり前に使われていた日本語が急速に失われている昨今、なかなか情景を思い浮かべることは難しい。
釣忍
◆なぜ鏡花に挫折してしまうのか その二 「夢かうつつか」の世界
「薄紅梅」にでてくる言葉「夢かうつつか」のとおり、鏡花の作品は「うつつ」の途中で「夢」になり、また「うつつ」へと…と行ったり来たりである。理詰めで考えがちな現代人にすれば、「夢かうつつ」の世界のなかで道を失って途方にくれて挫折してしまう。
◆なぜ鏡花に挫折してしまうのか その三「尾花を透かして、蜻蛉の目で」視点
「薄紅梅」に何回か繰り返される印象的な歌部分を抜き出してみた。
ここから、南瓜の葉がくれに熟と覗くと、霧が濃くなり露のしたたる、水々とした濡色の島田髷に、平打がキラリとした。中洲のお京さん、一雪である。
糸七は、蟇と踞み、
南瓜の葉がくれ、
尾花を透かして、
蜻蛉の目で。
南瓜の葉の陰から覗く景色は、何とも美しいことだろう。
芒の穂のあいまに隙間をつくって蜻蛉のような複眼でみる景色は、空間軸がねじれ、不思議な眺めだろう。
鏡花が書いたのはそうした世界。蜻蛉の複眼をもたない身の哀しさよ、私たちが挫折するのも無理もない。
◆でも挫折の原因は鏡花の魅力だったりもする
いにしえの言葉「百蓮華」とか「未開紅」は、辞書をひかなければ意味も分からないけれど、その言葉の美しさにまず惹かれる。鏡花作品は、意味はよく分からないけれど美しい言葉を散りばめた万華鏡。
「夢かうつつか」も、「蜻蛉の目」も理詰めで筋を考えていけば迷子になる。でも心にひろがる不思議な光景にひたれば、それは心地よいものではなかろうか?
◆「うつつ」から「夢」へ、また「うつつ」への跳躍、不思議な赤蜻蛉視点が入り混じる魅力を「薄紅梅」お気に入りの箇所「三」で考えてみた!
古本屋の女房の昼下がりを描いた「うつつ」の文(青字)が、赤蜻蛉の飛行を描写する赤蜻蛉視点の文(赤字)のあと一転して、釣忍を人に見立て、古本屋の女房と戯れるエロチックな夢の場面へと変わる(ピンク字)。「――こういう時は、南京豆ほどの魔が跳るものと見える。――」と鏡花の声が響き、また「うつつ」へと変わる。
一つの章のなかに、これだけ「夢」「うつつ」「赤蜻蛉の視点」が入り混じる。そして、この綱渡りが作品全体にひろがっていくのである。鏡花作品に挫折するのも無理はない。同時にこの不思議な世界に憧れるのも無理はない。
泉鏡花「薄紅梅 三」より
遅い午餉だったから、もう二時下り。亭主の出たあと、女房は膳の上で温茶を含んで、干ものの残りに皿をかぶせ、余った煮豆に蓋をして、あと片附は晩飯と一所。で、拭布を掛けたなり台所へ突出すと、押入続きに腰窓が低い、上の棚に立掛けた小さな姿見で、顔を映して、襟を、もう一息掻合わせ、ちょっと縮れて癖はあるが、髪結も世辞ばかりでない、似合った丸髷で、さて店へ出た段取だったが……
――遠くの橋を牛車でも通るように、かたんかたんと、三崎座の昼芝居の、つけを打つのが合間に聞え、囃の音がシャラシャラと路地裏の大溝へ響く。……
裏長屋のかみさんが、三河島の菜漬を目笊で買いに出るにはまだ早い。そういえば裁縫の師匠の内の小女が、たったいま一軒隣の芋屋から前垂で盆を包んで、裏へ入ったきり、日和のおもてに人通りがほとんどない。
真向うは空地だし、町中は原のなごりをそのまま、窪地のあちこちには、草生がむらむらと、尾花は見えぬが、猫じゃらしが、小糠虫を、穂でじゃれて、逃水ならぬ日脚の流が暖く淀んでいる。
例の写真館と隣合う、向う斜の小料理屋の小座敷の庭が、破れた生垣を透いて、うら枯れた朝顔の鉢が五つ六つ、中には転ったのもあって、葉がもう黒く、鶏頭ばかり根の土にまで日当りの色を染めた空を、スッスッと赤蜻蛉が飛んでいる。軒前に、不精たらしい釣荵がまだ掛って、露も玉も干乾びて、蛙の干物のようなのが、化けて歌でも詠みはしないか、赤い短冊がついていて、しばしば雨風を喰ったと見え、摺切れ加減に、小さくなったのが、フトこっち向に、舌を出した形に見える。……ふざけて、とぼけて、その癖何だか小憎らしい。
立寄る客なく、通りも途絶えた所在なさに、何心なく、じっと見た若い女房が、遠く向うから、その舌で、頬を触るように思われたので、むずむずして、顔を振ると、短冊が軽く揺れる。頤で突きやると、向うへ動き、襟を引くと、ふわふわと襟へついて来る。……
「……まあ……」
二三度やって見ると、どうも、顔の動くとおりに動く。
頬のあたりがうそ痒い……女房は擽くなったのである。
袖で頬をこすって、
「いやね。」
ツイと横を向きながら、おかしく、流盻が密と行くと、今度は、短冊の方から顎でしゃくる。顎ではない、舌である。細く長いその舌である。
いかに、短冊としては、詩歌に俳句に、繍口錦心の節を持すべきが、かくて、品性を堕落し、威容を失墜したのである。
が、じれったそうな女房は、上気した顔を向け直して、あれ性の、少し乾いた唇でなぶるうち――どうせ亭主にうしろ向きに、今も髷を賞められた時に出した舌だ――すぼめ口に吸って、濡々と呂した。
――こういう時は、南京豆ほどの魔が跳るものと見える。――
パッと消えるようであった、日の光に濃く白かった写真館の二階の硝子窓を開けて、青黒い顔の長い男が、中折帽を被ったまま、戸外へ口をあけて、ぺろりと唇を舐めたのとほとんど同時であったから、窓と、店とで思わず舌の合った形になる。
女房は真うつむけに突伏した、と思うと、ついと立って、茶の間へ遁げた。着崩れがしたと見え、褄が捻れて足くびが白く出た。