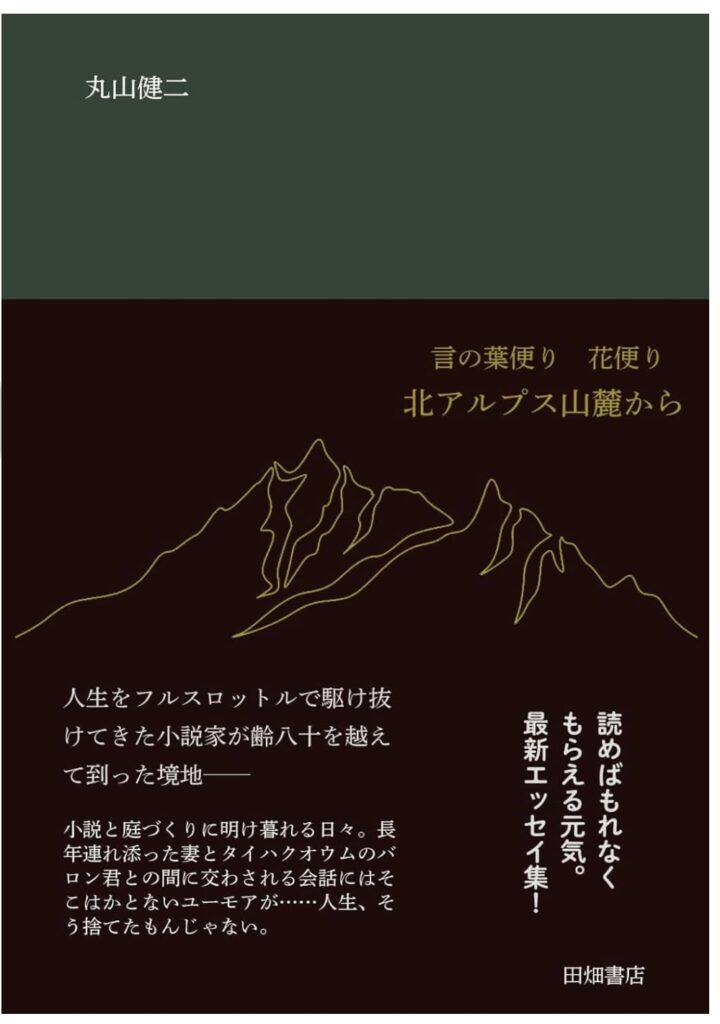丸山健二『言の葉便り 花便り 北アルプス山麓から』より「死が癒してくれるよ」を読む

八十一歳を迎えた丸山先生の、どこか自分を無理やり鼓舞するような思いが私には感じられた。
まず以下引用文のように、ズバリ言い切る。
つまり消えてなくなるのが存在の宿命なのです。
(丸山健二『言の葉便り 花便り 北アルプス山麓から』60ページ)
さらにこう続ける言葉は、どこか丸山先生自身に言い聞かせるようにも響いてくる。草花を見て、ここまで思うのは大町の自然の中に暮らす丸山先生らしい。
もしかしたら高齢者が夜遅くまで辛そうな顔をして働いている都会にいたならば、「散り際の幸い」を望む声が聞こえてくるのかもしれない。大町に暮らす大変さと同時に素晴らしさを思う。
開花を間近に控えた千草も、満開を迎えた花木も、当然ながら散り際の美などを念頭に置いてはいないはずです。ましてや朽ち果てる定めに付き纏う醜についてもいっさい思い浮かべたりはしないでしょう。
生物としての存在はかく在るべきです。そう思うことに決めました。
(丸山健二『言の葉便り 花便り 北アルプス山麓から』61ページ)
以下引用文。瀕死のコオロギは丸山先生自身を託した姿なのだろう。その皮肉めいた声も、ボロボロの姿も心に突き刺さるものがあって、やはりこの世で生きていく大変さを思う。
「死が癒してくれる」という言葉も皮肉にしかならないこの世は、やはり大変」だなあと思う。
「何があったにせよ、いずれ死が癒してくれるさ」と皮肉を込めて呟いたのは、秋の終わりにデッキの下でぼろぼろの羽を声帯代わりにする、瀕死のコオロギでした。
(丸山健二『言の葉便り 花便り 北アルプス山麓から』61ページ)