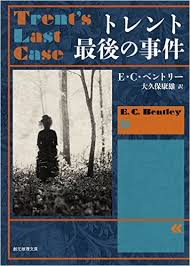「トレント最後の事件」
著者:E・C・ベントリー
訳者:大久保康雄
初出:1913年
東京創元社
富豪の殺人をめぐるミステリ。
この富豪の印象的な描写が随分でてくるけれど、その部分を組み立てて考えると、人物がうかんでこない…こんな人物がいるだろうか、いるはずがない、という白々しい気持ちに少しなってしまうけど面白い。
1913年、英国育ちのベントリーが、ヨーロッパよりも好調なアメリカ経済を牽引するほどの人物の殺人事件を描く…というのは少し無理だったのかなあとも思う。
でも当時の教養ある英国人が、アメリカの富の頂点にいる人達のことをどう思っていたのか、本音が聞こえてくるという点で興味深い作品である。
富豪の妻が語る言葉は、ベントレーの考えそのものではないだろうか。
「あれほど老獪な彼のことですから、口に出さなくとも、きっと心の中ではわかっていただろうと思いますーわたくしよりも二十歳も年上で、大きな事業上の責任を負い、人生の全部を事業にそそぎこんで他のものをかえりみなかった人ですから、わたくしみたいに音楽や読書や非現実的な思想で育てられ、一人で楽しむことを好きな女を妻にすれば、大きな不幸をまねく危険のあることくらい、わからなかったはずはないと思うのですが、でも彼は実際にわたくしを、その社会的地位にふさわしく、十分に彼の名声を引き立ててくれる妻だと、本気で思いこんでいいたのです」
上顎が総義歯の富豪が二十歳下の美女を妻にしたときに、そんなことまで求めはしないだろうに…と思ってしまうが。
「その世界では、生きるためには、ものすごく金持でなければならなかった―金のことしか問題にされず、金以外のことは何も考えない世界です。巨万の富をつくった人たちが、仕事に疲れたときや、余暇ができたときに夢中になるのは、せいぜいスポーツだけです。働く必要のない人たちは、働かなければならない人たちより、はるかに退屈で、しかも非情にたちが悪いものです」
「せいぜいスポーツだけ」なんて、ここまで書かなくても…と思ってしまう。でもアメリカのお金持ちは、そんなふうに英国人に言われるくらいに勢いをつけはじめていた時代なんだろう。
でも富豪像への疑問はつきない。妻の部屋よりも小さく、質素な部屋で暮らしているのに、靴道楽? 性格は悪いが、嘘はつかない? 嫉妬にかられて狂気のひとになる? 殺される人物だから、人間性に統一がなくてもよいものなんだろうか? ミステリの世界はわからない。
訳について少し引っかかった箇所をメモ。
that it was a lie put out by some unscrupulous “short” interest seeking to cover itself. 「いや、から売りしていた不届きな連中が、それをごまかそうとして流したデマだろう」(大久保康夫訳)
「それは嘘だよ。節操のない空売り筋が、利益をとろうとして嘘をながしているんだ」…という意味なのでは?
I felt that the only possible basis of our living in each other’s company was going under my feet. And at last it was gone.
「わたくしは、同棲をつづける唯一の理由が、だんだん薄らいでいくような気がしていたのですが、それがとうとう消えてしまったのです。」(大久保康夫訳)
living in each other’s company は「一緒にくらす」という意味だが、「同棲する」と訳すとまだ少しは愛情がある気もするが、ここで言いたいのは「一緒に暮らしているだけ」という冷えた感じなのではなかろうか?
going under my feet は「薄らいでいく」というよりも、もっと鬱陶しい気持ちが込められていて「気に障る」というような意味ではなかろうか?
読了日2017年7月22日