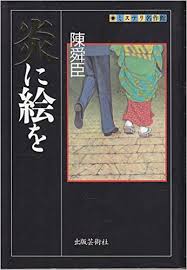「炎に絵を」
著者:陳舜臣
初出:1993年
出版芸術社
読書会にむけて再読。とりあえず疑問をメモ。
・欠けている部屋とは?
「嫂の伸子の手によって、きれいに整頓されているが、それでもなにか欠けているかんじがする」3頁
―冒頭に「欠けている」という言葉があると、何が欠けている一家なのだろうと思わず立ちどまって考えてしまう。そこまで考えた書き方なのだろうか。
これから先はネタバレあり
・順子の言葉の奥にあるものは?
「ママはひとりよがりよ。いくら整理したって、自分にしかわからないやり方なら意味ないわ。想像力がないのね。ほかの人にもわからせるってことができないんだもの」
「さんざん苦労かけてるのに、ママのわる口なんか言っちゃいけないよ」
「だって、あたしだったら、ちゃんと…」
高校一年生の順子は、口をとがらせた。
火のついていないたばこをくわえたまま、省吾は机の上を見た。順子のノートが、そこにひろげられている。ところどころに、緑色の鉛筆でギザギザのアンダーラインが引いてあった。(3~4頁)
―これはただの母子のすれ違いのようにも、それとも犯罪実行をめぐる意見の相違があったようにも思えてくるが。どうなのだろうか?
・嫂一家の金への渇望ぶりについて、ほのめかしが一切ないのは如何なものか?
250頁「あたし、マンションを借りようかしら…冷暖房完備、いつでもお湯が出るし、よけいな手間がかかりませんから、一人暮らしには便利でしょう」
254頁「ピアノがあったら」
―最後250頁になるまで、嫂一家がそこまでお金をほしいと思わせるヒントがない気が…。
犯人の意外性を楽しませようとする設定なのだろうか。
でも途中で嫂一家のお金、姪のリッチな生活への憧れをちらりとでも書き、欲張りな顔、清純な顔の落差を途中で楽しむ読み方もしたい気がするが、どんなものだろうか?
・一郎が病の床で恐れていたものとは?
「あとのほうになると、肩にかぶさった毛布が、眼にみえて揺れた。唇が痙攣しているのが、まるでなにかを恐れているかのようだった。」
―恐れてるのは家族への心配か、犯罪実行がうまくいくかどうかの恐れなのか?
・省吾について
「うしろは山で、まえが海。からっとしたところだ。きみの性格に似てるかな」26頁
「彼はいまや富豪であるが、それは順子の両親のはからいによって、そうなったのだ」255頁
「おれの胸のなかで、このことは葬ってしまわなければいけない」261頁
「立ちあがったとき、彼の膝からおちた『母の像』は、裏がえって、畳のうえにあった。
省吾の足は、それを踏みつけていた。」
―踏みつけていたのは意識的にですよね? 両親のはからいで…と言っておきながら、これは許せない気が。「葬ってしまわなければ」というのも許せない気がします。
・諏訪の旅館の場面には無理があるのでは?
―夜十時頃諏訪をでて、順子はどう家に戻ったのか?駅で野宿したのか?
―なぜ熱燗にする必要があったのか?八月の諏訪で熱燗を飲みたいものか?275頁に「女中に訊かれたので、熱燗にしてほしい、と答えたのだろう」とあるが、私が順子ならサッとだせるお冷を諏訪子にだしたいところだが。
―知らない旅館に女中さんとして潜りこむ設定には無理があるのでは?
・倒れてきた鉄板は?
69頁の鉄板が倒れた場面、どうも場面が思い浮かばないのですが。
・「本職は、貿易業で、神戸に暮らしています。神戸生まれ、神戸育ちで、まァ神戸っ子というわけです。本籍は台湾ですが。
年齢満39歳。金もうけにも文学の仕事にも闘志満々というところです」
(レジャーの窓「作者は語る」の陳舜臣の言葉、陳舜臣展覧写真の41枚目あたり)
作家で「金もうけに闘志満々」と明言する方は珍しいような気がして、この言葉は記憶に残った。
この作品でも、少しでも金を貰おうとする使用人、植原、富沢のふたり、公認会計士の春名については目にうかぶように書いている。
華僑の大富豪も、諏訪子についても人物がうかんでくる。
たぶん実際にこういう富豪たちを目にしてきたのではないだろうか。
でも貧しい嫂一家はどうも浮かんでこない。読んでも暮らしが逼迫しているという感じが伝わってこない。陳舜臣は、あまり貧乏な人間と付き合いがなかったのでは…という気がした。
読了日:2017年8月21日t