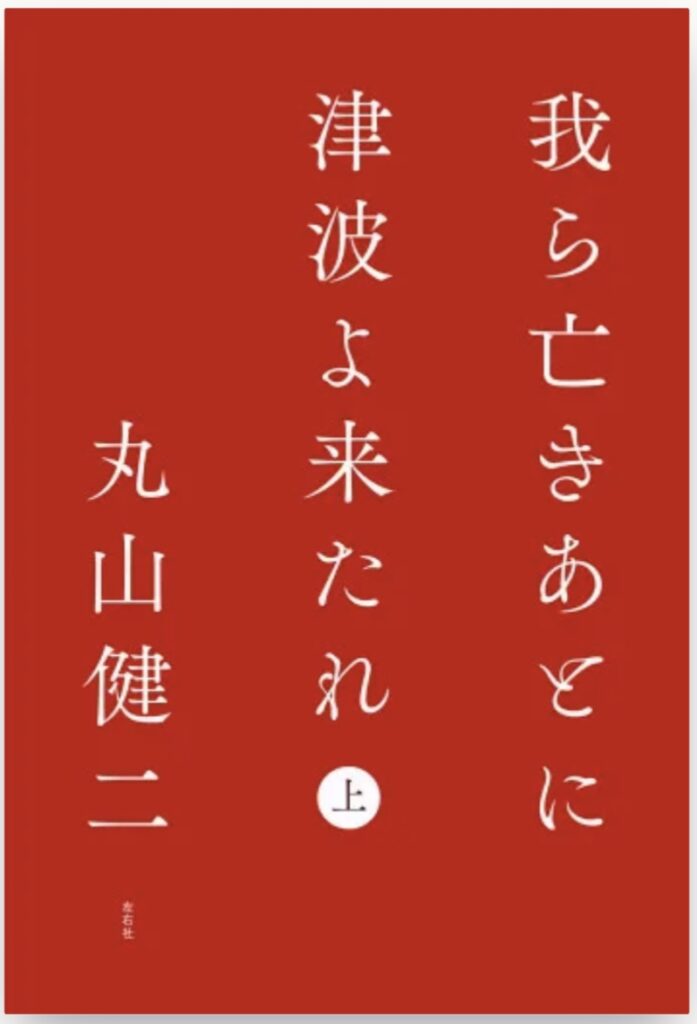丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」上巻を少し読む
➖天気の急変の描写に社会への思いを重ねた比喩の面白さ➖

大津波から助かった青年が見つめる星空の空模様が、だんだんあやしくなってゆく。
天気の移り変わりにかぶせるようにして、あっけなく崩壊してゆくこの世の思想のあれこれを列挙して畳みかけてくる。
そうした喩えのイメージから聞こえてくる音、伝わってくる不穏な気配が、雷雲が近づく空模様と重なって読み手の心に揺さぶりをかける。
喩えの一番最初に「政府なき自由」がきている。
個人がそっと心の中で国家に背を向ける「国境なき意思団」という考えが大切……とよく語られる丸山先生らしいと思う。
あれほどまでに澄みきって晴れ渡り
流星群が光の鎖をなして降り注いでいた
深い瞑想による清らかな暮らしをどこまでも支えてくれ
単独の人間の行為のうちにいつまでも安んじていられそうな夜空が、
政府なき自由が嵐を巻き起こすという、
魂の炎さえ絶やさなければ恒久的に生を燃え立たせられるという、
真に恐るべきは群衆のなかの一員に堕することであるという、
辛抱強く待ち望めば道徳的な生活は実現するという、
人の心の善良性は思うがままに疾走するという、
精神の欠如によって命の影が薄まるという、
理性に反する美は死に絶えるという、
体勢への順応主義は去勢されるという、
悪が生の揺籃の役割を果たすという、
そうした種概念の
得手勝手な主観の持つ理念のように
どんどん怪しくなっていった。
(丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」上巻171頁)