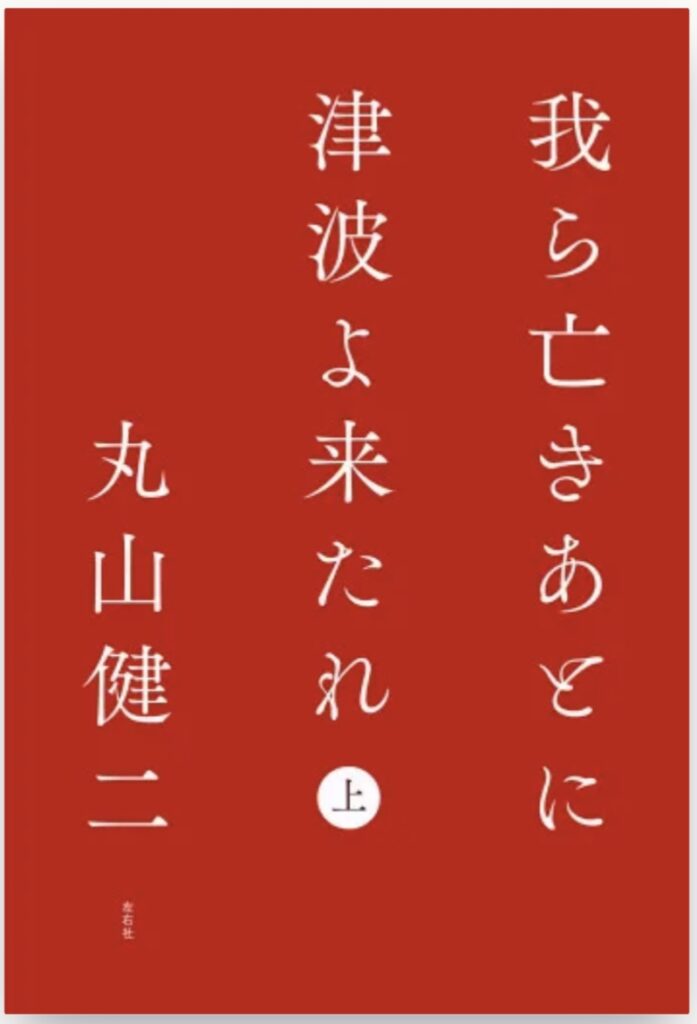丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」上巻を少し読む
ー自分のドッペルゲンガーを前にした時に思い出されることを言葉にすればー

津波から助かった青年が無人の被災地をさすらううちに、自分の家にたどり着く。
我が家の新台には、裸で男が死んでいた。
よく見れば、その死んだ男は自分自身だった……。
以下引用の長い、でも一つの文は、そんなドッペルゲンガーを見つめ埋葬を決意するまでの、青年の心に思い浮かんでくるあれこれを語っている。
長い文の最初は「波打つ草のごとき切なる追想に耽りつつ」と引き込むような美しい言葉で始まる。
そして続くドッペルゲンガーと「たわいもない局部的な過ちの染みについて」交わす会話。
その内容は具体的には書かれていない。
そのかわりに「たとえば」と繰り返すことで、読み手の方でイメージをどんどん膨らませていくことができる。
そう、一番最後の「たとえば」だけ、「娼館を女手ひとつで切り回していた育ての親」とやけに具体的なのはなぜなのだろうか?
読み手の意識を現実に引き戻す合図だろうか?
一つの文の中に、作者の意図が色々働いている気がする。
しばしのあいだ、
波打つ草のごとき切なる追想に耽りつつ
たわいもない局部的な過ちの染みについて
もうひとりの自分かもしれぬそいつを相手に無言の語らいを始め、
たとえば
神格化が可能なほど絶対的な孤立、
たとえば
おのれの涙にまみれた明けの明星、
たとえば
本来の人間に帰するための動と反動、
たとえば
中間的な存在である万物がもたらす粗雑な結果、
たとえば
八方の境界を超えてほとばしる新しい眺望、
たとえば
憎しみが恍惚に昇華してしまう光明なき時代、
たとえば
逃避を許さぬ荒涼たる空虚、
たとえば
娼館を女手ひとつで切り回していた育ての親、
そんなこんなを
思いつくままに喋りまくったあと、
地面の下が本当にふさわしいかどうか
念入りに再確認しようと
もう一度遺骸の前にしゃがみこんだ。
(丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」上巻455頁)
丸山先生も、短歌の福島先生も共通するお叱りのフレーズは「それは説明的すぎる」という言葉。
わかりやすく書くのではなく、かけ離れた語と語を結びつけてイメージの花束を読み手に差し出す……ことを理想とされているのではないだろうか。
読み手は、差し出された言葉の花束を自分の思考回路に流して自由に造形していく……という読み方を、丸山先生も福島先生も理想とされているのかもしれない……とふと思った.