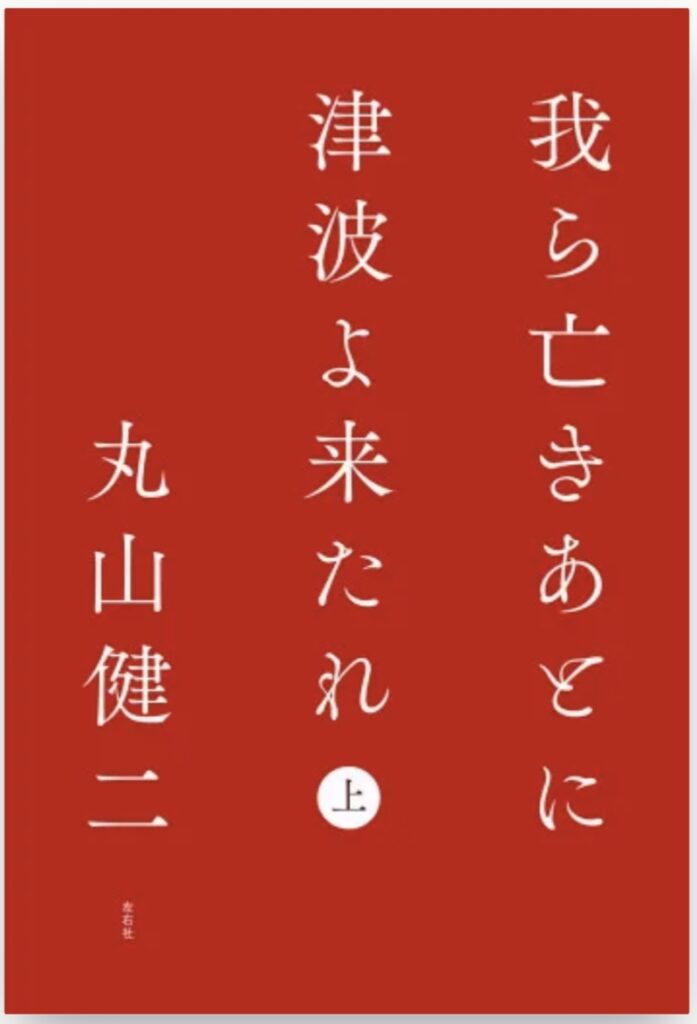丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」上巻を少し読む
ードッペルゲンガーの存在に疑念を抱かせない語り方ー

若い頃、歌人・高瀬一誌から指導を受けた歌人(福島先生ではありません)にこう教えて頂いた。
高瀬一誌が常々言っていたのは「他人と似ていない歌をつくれ」との言葉だと。
高瀬一誌に指導を受けたその方は「短歌は長くつくっているうちに自分の文体ができてきます」とも励ましてくださった。
小説でも、文芸翻訳でも「他人と似ていない」「自分の文体」ということは、あまり大事にされていない気がする。
(今の厳しい出版社サイドにすれば、少しでも多く売れてくれる……だけで精一杯なのかもしれないが。)
だが丸山先生も、そういう視点をすごく大事にされていると思う。
丸山先生の今の文体は、「丸山健二」という名前がなくても、一目でパッと「丸山先生の文だ!」と分かる。
そして私も、丸山先生とも似ていない自分の文体を作らなくてはいけない……とは思うが、いつになるやら。
でも「他人と似ていない」「自分の文体」を目指すところが、短歌や散文を書く醍醐味であり、苦労なのかもしれない。
さて「我ら亡き後に津波よ来たれ」だが……。
津波を逃れた青年は無人の被災地をさすらううちに、見覚えのある我が家にたどり着く。
中に入れば、寝台には裸の男。
よく見れば、男は死んでいた……
さらによく見てみれば、死んだ男は自分自身。
自分のドッペルゲンガーを見ているのだった。
そんなドッペルゲンガーとの出会いにつづく文は、不思議な状況に疑念を挟む隙を与えないような、格調の高い文だと思う。
「獄門が閉ざされてから吹き渡る」「上々吉の風」「異形の風」「裁きの庭のごとき」「夜々草のしとねに伏す悲しみ」「静かに輝く草原というたぐいの夢さえ尽き果てた現世の暗闇」……と畳みかけられたら、ドッペルゲンガーがたしかにいる気になってくるではないか!
また
ほんの少し視点を変えれば、
獄門が閉ざされてから吹き渡る上々吉の風とは真逆の
異形の風に導かれて可能になったこの異様な出会いは
永遠に未熟な魂同士の融合と言えるのかもしれず、
さもなければ
震撼の世におけるただ一度の歓喜の巡り合いということなのかもしれず、
早い話が、
特異な性格を具えた異端者同士が
生々躍動する秩序の崩壊にあまねく覆われた
あたかもたじろぐしかない戦いの場のごとき
もしくは裁きの庭のごとき
この被災地に濃い影を落としていることになるのやもしれず、
そして今後は、
夜々草のしとねに伏す悲しみを負う胸のうちをぶちまけ合い、
互いに赦し合い、
心地よい孤独を知覚し合い、
肝胆をかたむけて一夜語り合い、
思い詰めた瞳の奥に折り重なる言葉の影をつぶし合い、
大気に孔をうがつほどの光の狂乱を夢見合い、
天高く輝く魂の避難所という幻想を徹頭徹尾無視し合いながら、
静かに輝く草原というたぐいの夢さえ尽き果てた現世の暗闇を
手に手を取ってさまようことになるのかも知れなかった。
(丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」上巻407頁)
ただしドッペルゲンガーも登場してやや経過すると、だんだん語り方が砕けたものになってくる。
おかげで青年や読み手とドッペルゲンガーとの距離が、縮まったようにも思えてくる。
それからドッペルゲンガーとの距離を喩える表現の連続「遠方の恋人同士」から始まる文も面白いなあと思った。
早い話が、
おれはどこまでもおれでありつづけ
そ奴はあくまでそ奴でありつづけ、
相手はというと、
無に等しい罪深さしか知らぬ
未確定な未来への到達を心待ちにし
常に喜びもまたひとしおといった面貌の
死後の幸福までまんまとせしめてしまうような楽天家であり、
当方はというと、
夢見ることもあたわぬ
怒るにつけ悲しむにつけ眼下に心の碧譚を望むしかない
そうであればこその苦境に追いこまれつづける
流竄の詩人であって、
ともあれ、
両者はそれ以外の何者でもなく、
遠方の恋人同士のように、
離婚して久しい男女のように、
別々の飼い主に引き取られた仔犬のように、
暗黒の空間ですれ違う小惑星のように、
互いに干渉し合う必要などない存在だった。
(丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」上巻421頁)