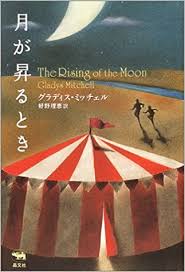「月が昇るとき」
著者:グラディス・ミッチェル
初出:1945年
訳者:好野理恵
出版社:晶文社
ISBN 4-7949-2743-6
日比谷海外ミステリ読書会の次回(9月24日午後日比谷図書館)課題本である。
この課題本に決定した直後、「相当しぶい課題本ですが参加者は集まりますかねえ」とか、「ますます会がディープになっていく」といろいろ心配して頂いた。
でもミステリビギナーの私にすれば、読後、「こんなに面白いミステリがあったんだ!」とミステリのイメージを大きく変えた一冊である。なぜグラディス・ミッチェルの本があまり翻訳されていないのかが不思議に思えるくらいに気に入った。
本書の内容は、帯によれば「月下の切り裂き魔。運河の町で発生した切り裂き魔による連続殺人事件を、13歳の少年の目を通して描き、不思議な詩情をたたえたグラディス・ミッチェルの傑作」とのこと。
でも帯にも、解説にも、この作品のおもしろさは書かれていない。解説のYさんとは、訳者だろうか?イニシャルだけの解説というのも初めてだなあ…イニシャルだけなら、こんな真面目に書かなくてもいいのに…と思ってもしまう。
もしかしたら、どこが大傑作なのかなあ…と迷いつつ訳されたり、編集されたりしたのだろうか。
訳書解説のどこにも書かれていない「月が昇るとき」のおもしろさとは? なぜ本作品が彼女の代表作なのかを知りたい方は、ぜひ9月24日午後日比谷図書館にて、宮脇孝雄先生の説明を聞いて考えてみませんか。
これから先はネタバレあり、不要の駄文。
すこし不気味、でもクスリと笑いたい、最後にはひたすら美しいものを読んだ…という気がする読後感は、澁澤龍彦の『人形塚』に通じる感じ。澁澤がグラディス・ミッチェルを読んだら、気に入ったんじゃないかなあと思う。
注文した原書が届いていないので何とも言えないところはあるけれど。
骨董屋の女主ミセス・コッカートン、最初は少年の心の友のような存在だったけれど、その彼女の化けの皮が一枚ずつはがれていく面白さ、それがミステリの謎ときのヒントにつながる楽しさが第一にあると思う。
礼儀正しく、古風だったミセス・コッカートンが最後に大鍋にむかっている場面の怖さ、面白さ。ここでミセス・カートンが鍋にむかいながら、手毬歌ではないけれど、何か歌をうたえば更に不気味でよいのになあ。
これも澁澤と通じるところだが、子供の視点で描いているからと言って、いかにも子供らしい子供を描かない。殺人事件を知って「この殺人事のおかげで、休みの間じゅう、ずっと面白いことになるかも」(47頁)と語る率直さも楽しい。
解説には「グラディス・ミッチェルの面白さが、物語のツボをあえて外していくオフビートな語り口にある」と書かれているが、どうでしょうかねえ。英国流に笑いのツボをせめていく正統な書き方をしているようにも思えるが。
九月の読書会で、宮脇先生、少ないと予想される参加者の皆様からのご意見を楽しみにしています。
読了日2017年7月9日