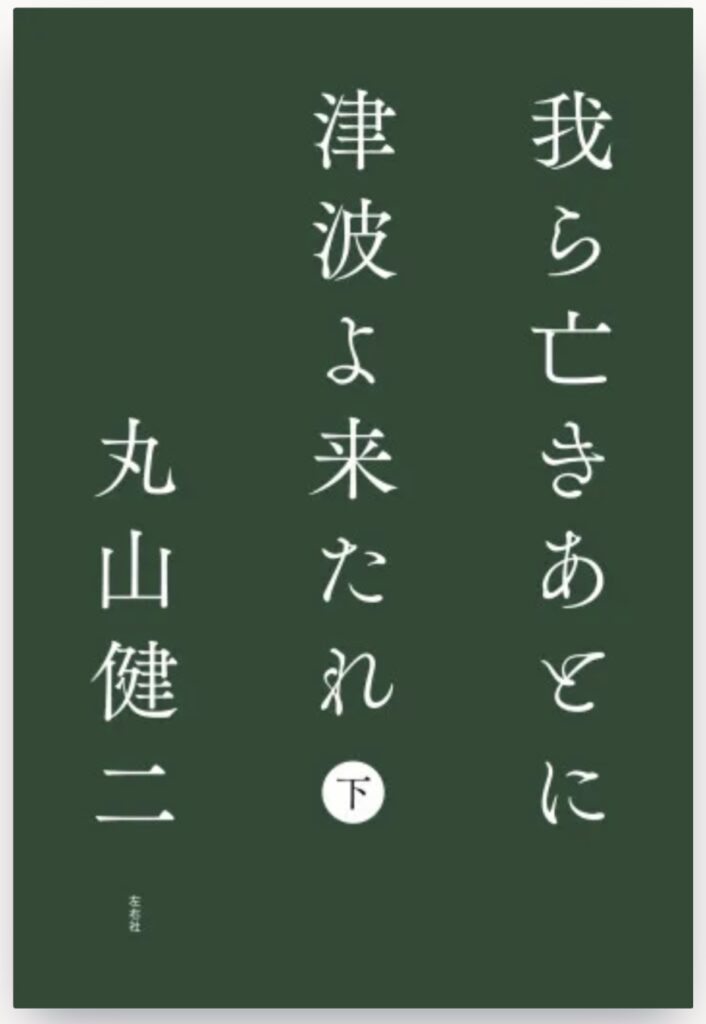丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」下巻を少し読む
ー平仮名、カタカナのさりげない選択で文が生き生きしている!ー

津波から助かった青年が、おのれのドッペルゲンガーを眺めるうちに自死した記憶、義母の介護の苦労を思い出し、ついには義母を殺してしまう。
引用箇所は、殺義母が最後の声にもならぬ声をあげて死んでゆく場面。
これもワンセンテンスである。
入力していると、「ここは漢字なんだ!」「ここは平仮名なんだ!」と読んでいるときはスルーしていたことを発見する。
丸山先生は「漢字、ひらがなは好みで、感覚で」と言われ、
短歌の福島先生は(短歌という限られた字数のせいもあるのだろうか)「漢字は象形文字。視覚的効果がある」と漢字にしたい箇所、ひらがなにしたい箇所のこだわりがあるようなことを言われ、
ちなみに女流義太夫の越若さんは「ここは漢字で語りたい。ここは平仮名で語りたい」と謎めいたことを言われ……(越若さんの言葉、いまだにどういうことなのか私には分からない。だが浄瑠璃をやっている方には分かる言葉のようである)、
とにかく日本語は平仮名、漢字、そしてカタカナから出来ている豊かな言葉なのだなあと思う。
丸山先生も「好みで、感覚で」と言われつつも、漢字とひらがなをしっかり使い分けされている……と入力しながら思った。
「強烈な圧迫によってすっかり閉じられた声門からわずかに漏れるのは」の箇所も、「強烈な圧迫」という漢字は目にずいぶんとインパクトがある。
「わずかに」と平仮名のせいで弱々しく絶えてゆく様が伝わってくる。
最後の「ほとんど解脱にも似た 喜ばしい最終回答が浮上」という表現は面白いなあと思う。「浮上」のパンチが効いて、天国にこれから行くんだという感じがある。
「魂の震撼が、妖異なる託宣に魅せられる神秘的な自意識が、忘れようとして忘れられぬ養母の生涯を包みこみ、渾然たるその精神をまるごと捉え、」という箇所、嫌でたまらない義母の姿がふっと消え、生は抜けてゆけど尊い存在に思えてくる。
最後の「なんだか……なんだかそうとしか思えなかったのだ。」の平仮名だらけの箇所は、平仮名ゆえに青年の慟哭が伝わってくる気がする。
漢字、平仮名、カタカナから成る日本語はほんとうに奥が深いと思う。
でも「誰とも似ていない歌をつくれ」と高瀬一志の言葉を教えてくれた知人が示すように、誰とも似ていない文を書かなくては……いや下手すぎて、タドタドしすぎて誰とも似ていないかもしれないとも思う。
だから、
もはや真情の結晶とやらを拠り所にして言い飾ることが困難な、
やむをえぬ場合以外はけっして慈愛のたぐいをせがまないという
悟性的理性の欠如が顕著な、
良識によって行いと言葉を律することができず、
不撓なはずの魂を改めて採寸してみれば
無に等しいただのがらくたにすぎないという、
そんなどこまでも本能的な自分と化し、
そこへもってきて、
魂を劫掠されっぱなしの
因業な老いさらばえた女という
哀れな犠牲者の口もとに締まりがないのは
すっかりがたがきた身体が最終的な休息を要求しているからだと気づき、
また、
強烈な圧迫によってすっかり閉じられた声門からわずかに漏れるのは
恐怖の悲鳴でもなければ
呪いつづけてきた世間にむけて救いを求める言葉でもなく、
いずれ灰燼と化す運命にある慰安を探し求めるかのような
無限に細分化できる
移ろいやすい呻きのみで、
おぞましいにもほどがある
その音源の道筋をたどってゆくと、
意図とは異なる結果によって
これが最後の生存となり
もはやふたたびこの世に生を受けないという、
ほとんど解脱にも似た
喜ばしい最終回答が浮上して、
歪曲された生と死の一体性が、
京楽的営為の終局に訪れる魂の震撼が、
妖異なる託宣に魅せられる神秘的な自意識が、
忘れようとして忘れられぬ養母の生涯を包みこみ、
渾然たるその精神をまるごと捉え、
なんだか……
なんだかそうとしか思えなかったのだ。
(丸山健二「我ら亡きあとに津波よ来たれ」下巻268頁)