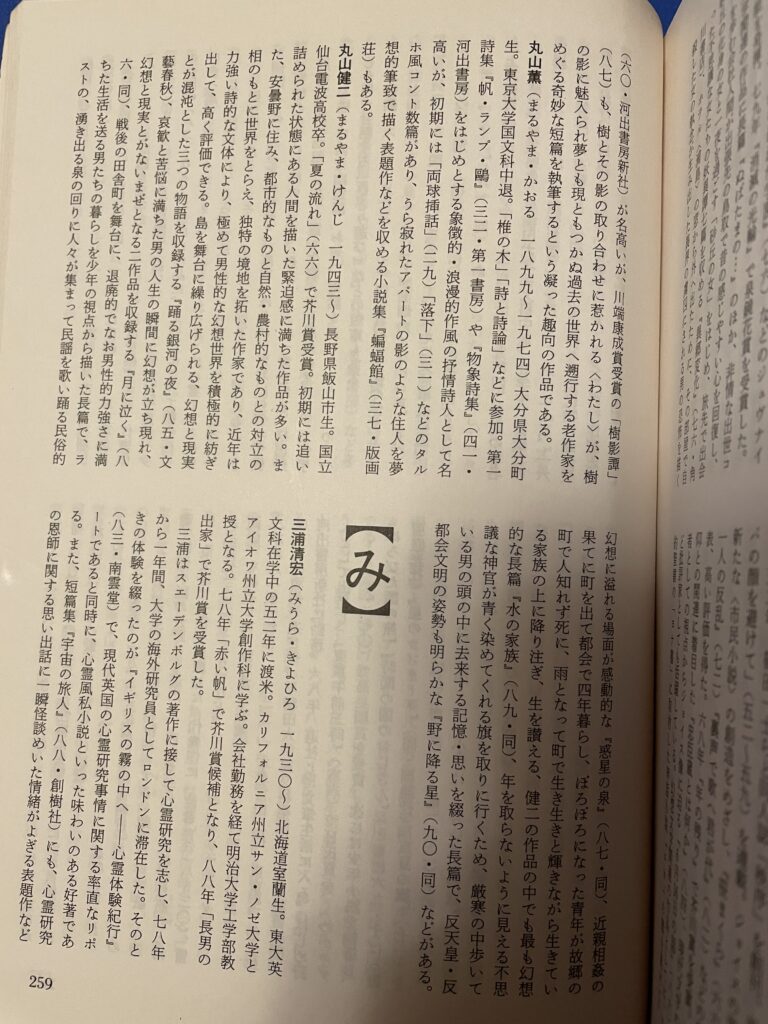丸山健二「トリカブトの花が咲く頃」上巻を少し読む
ーひとではない高原が語るおもしろさー

「トリカブトの花が咲く頃」の舞台でもあり、語り手である高原・巡りが原がおのれの役割について語る箇所。
他の丸山文学と同様、人でないモノ、高原が語るこの小説は幻想文学であると思うのだが、丸山文学を幻想文学として語った人は石堂藍から見かけない気がする。
丸山文学ファンは純文学としてのみ捉え、幻想文学としての魅力を語る人が殆どいないという現状をとても残念に思う。
標高千数百メートルに位置する
憐れみ深いこの地は
やむにやまれぬ理由でおとずれた者たちを
最後の手段として胸を圧する苦悶の縛めから解き放ってやり
この世にふたたび生を受けないようにしてやるための
すなわち
真の救済に直結する
神聖な死に場所なのだ
(丸山健二「トリカブトの花が咲く頃」上巻210頁)
巡りが原も、すっかり俗物となってしまった青年僧だけは我慢ならず、かくも語る。
高原が語るから、どこか距離を置いて読むことができるような気がする。
人間なら余計な感情が入り込んでしまうと思う。
つまり
月が太陽に席をゆずるたびに彼が支配力を強め
ついには
私をさしおいて「巡りが原」の主人と化してしまうことだ
それだけはどうにも我慢ならない
だから
なんとしても阻止する
またここで大往生をむかえさせるようなことがあってもならない
ここで死なれても私にはなんの慰めにもならないどころか
その腐肉の一片の果てまで溶けてなくなり
骨片のひとかけまで消え去ったあとでも
不快な気分は長いことつづき
そして
おぞましい残留物をすっかり追いはらえるようになるまでには
ひょっとすると
つぎの戦争と
そのあとに訪れる平和を待たなければならないかもしれない
(丸山健二「トリカブトの花が咲く頃」上巻223頁)

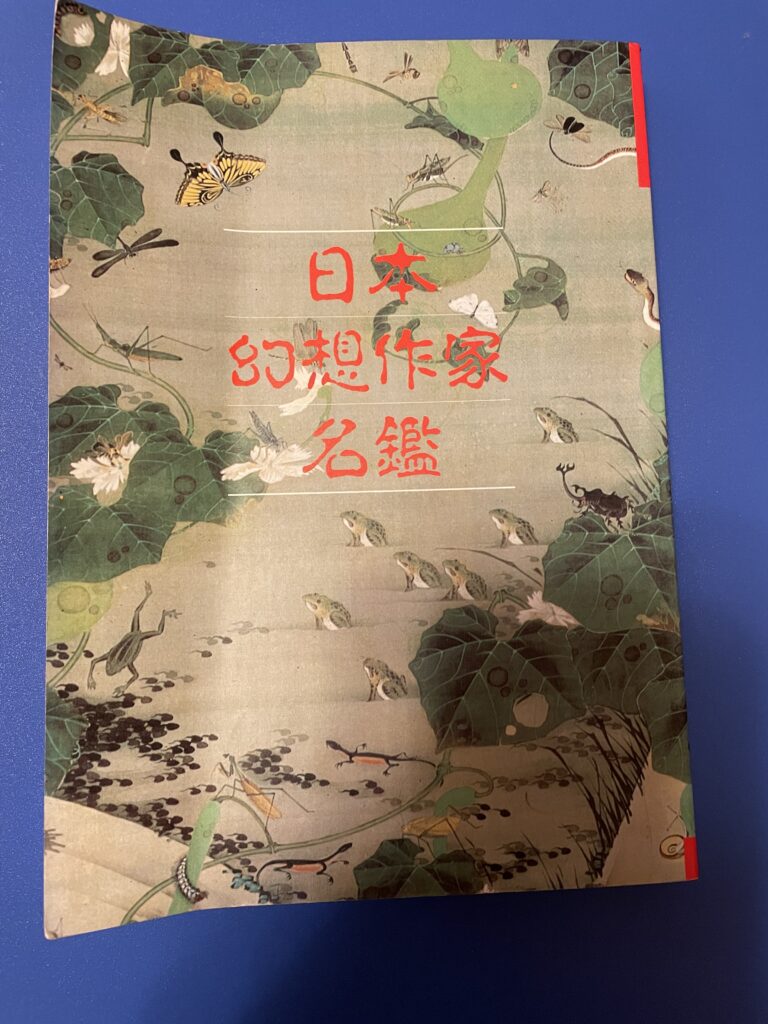
日本幻想作家名鑑に石堂藍が記した丸山健二の項目。