製本基礎講座29回 「改装本 角背 組み立て」
板橋の手製本工房まるみず組の製本基礎講座29回。引き続き改装本に取り組む。
表紙、帯、背、裏表紙のうち残しておかないといけない情報部分は残し、不要な部分は切り落として解体。
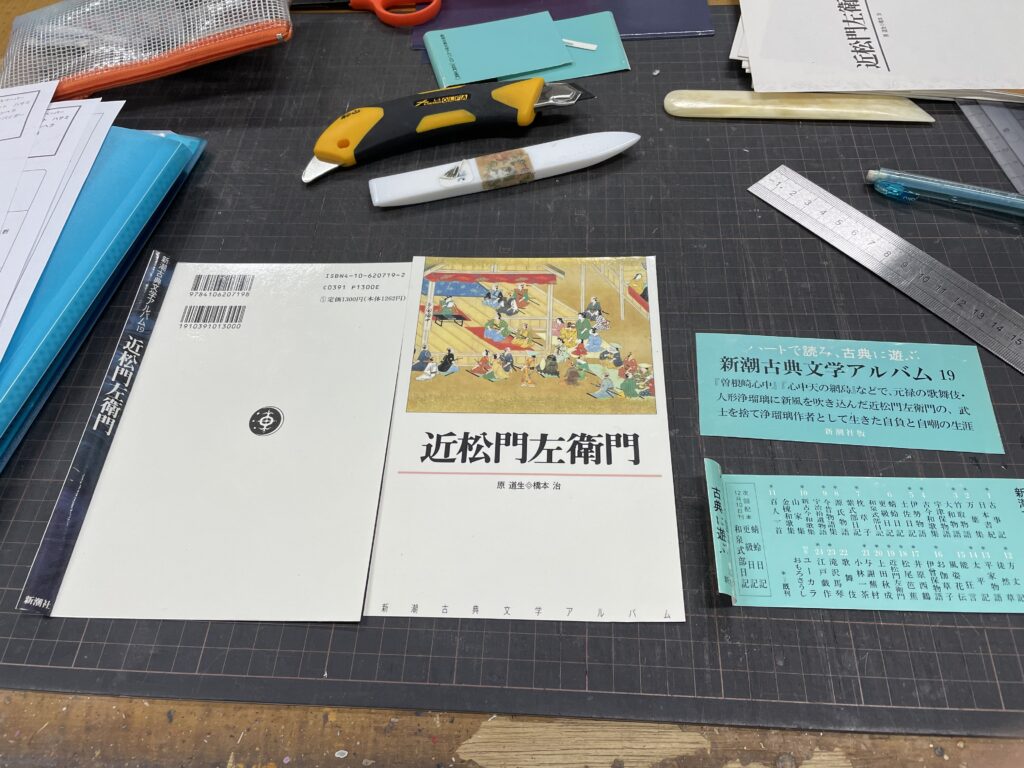
表表紙、背+裏表紙、帯前部分、帯後ろ部分+背に解体。さらに本文の大きさに合うように少し切断。↑
そして片端に「足」なるものを貼っていく作業。
何でもパッセカルトンの技法を少し取り入れたやり方だそう。まるみず組らしいやり方だなあと思う。
パッセカルトンにおける足とは……。調べてみたら、各折丁に同じ幅の「足」をつけ、その部分を綴じることにより、折丁がノドまでパカッとフラットに開くらしい。改装本の場合はどうなのだろうか。
本に足をつけることができるなんて知らなかった。
でも知らないこと、イメージできないことを作業するのは難しいもの。
下は作業後のもの。和紙の足がついている。貼るだけでは?と思うかもしれないが、ここでだいぶモタモタした。
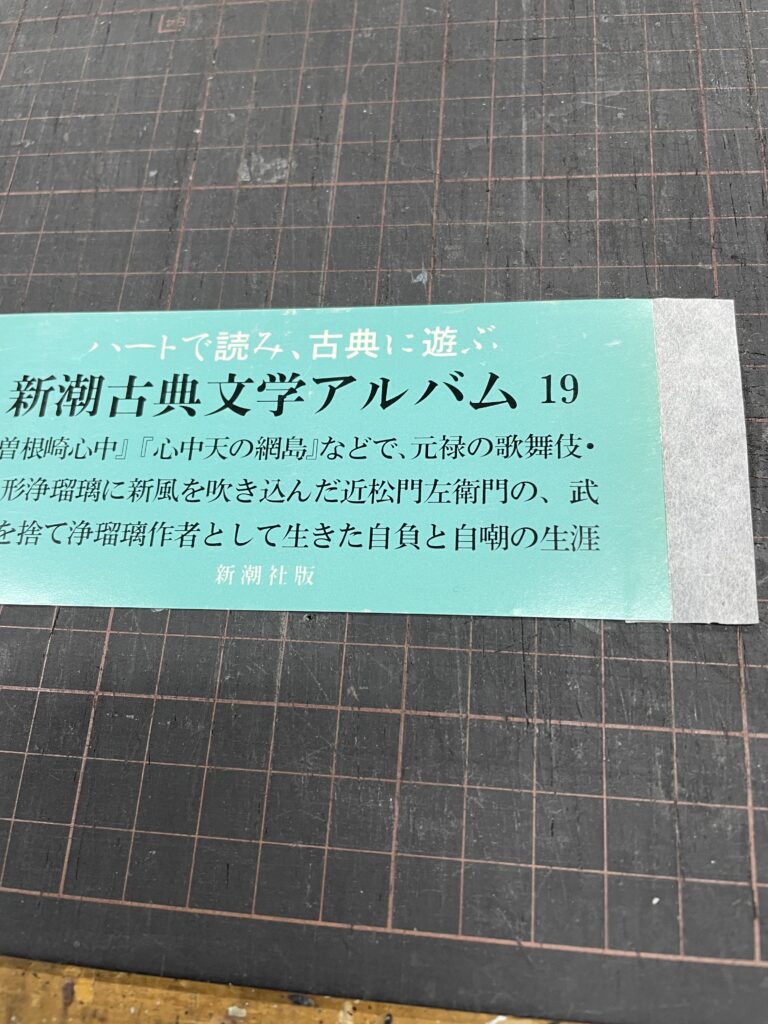

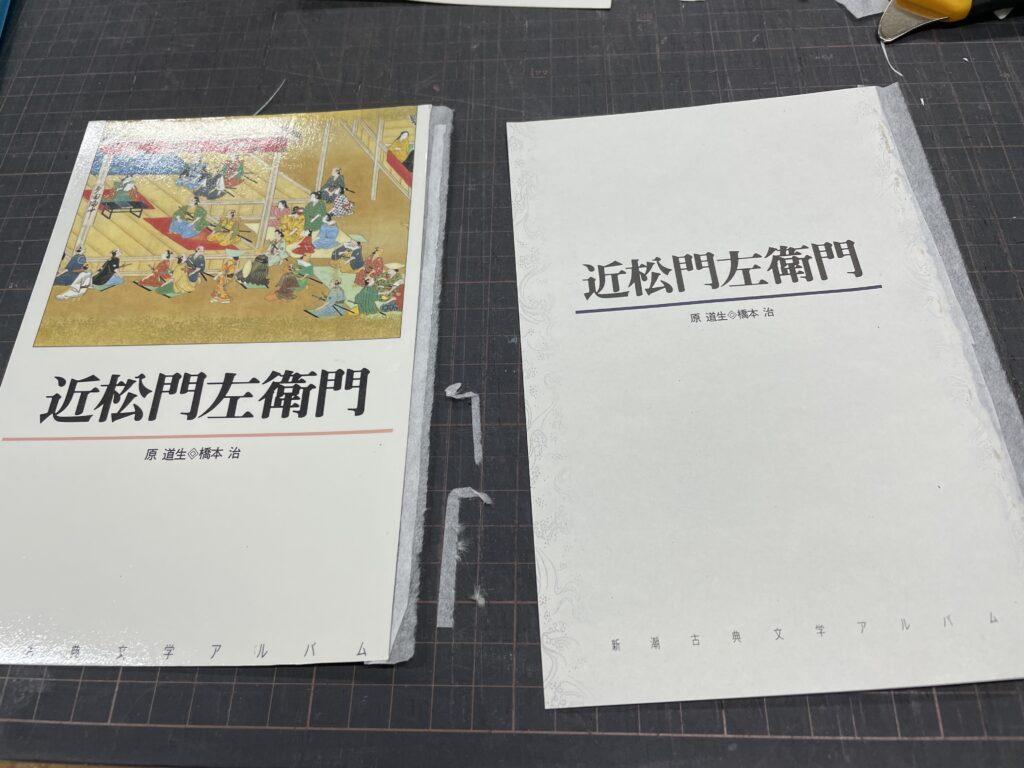
貼る位置を間違えたり、
ノリボンドを塗る箇所を逆に塗ったり、
足の切断箇所を間違えたり、
足の幅7ミリになる筈が足りなくなったり、と色々ミスが発生。
気づいてくださる先生も大変である。でも根気強く、分かりやすく教えてくださる。
この和紙の足を切り出す作業、家でやったら和紙がボロボロになった…と先生に言えば、色々気をつかうポイントを教えてくださる。先生のそばで切ると、ちゃんと切れる。不思議だ。
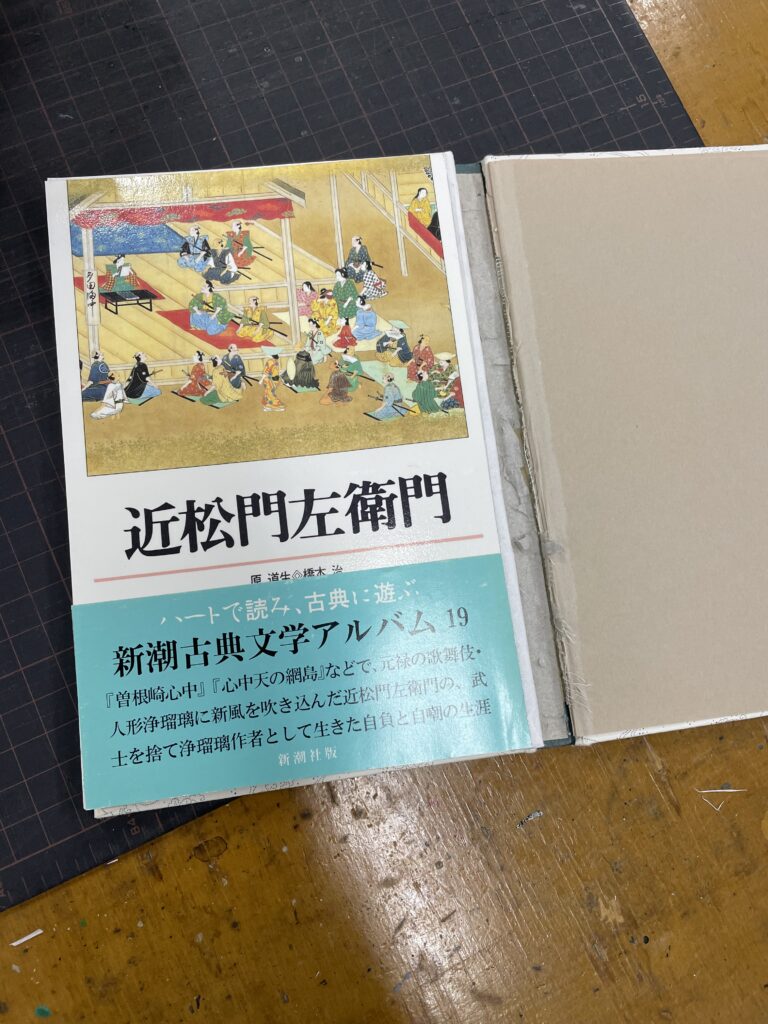
表紙の「足」で本文の最初の折丁を包み、さらに帯の足で表紙をくるむ。
後ろ表紙も同様にくるみ、何とか今日の作業は終了。
果たして家で復習したとき再現できるやら心許ないが。
