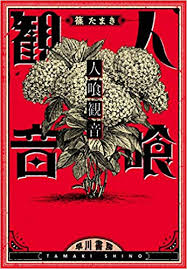作者である故・岡松和夫は1976年に「志賀島」で第74回芥川賞を受賞した作家。平井呈一の姪と結婚していた岡松和夫は、1993年に平井呈一と永井荷風の決別にいたる経緯を記した本書を発表した。
「断弦」では、平井 呈一 は「白井貞一」、永井荷風は「永江荷葉」という名前で登場。その他の登場人物も、読んですぐに誰なのか推量ができる名前である。
この小説は、平井呈一が大学ノート二冊に記した回想録を入手した作家「秋川」が書いたというかたちをとっている。そのノートがはたして実在したのかどうかは分からないが、本書ではノートの五分の一は英語、ところどころ噂の箇所は黒く塗りつぶしてあったと描写されている。
「断弦」のどこまでが真実かは不明だが、芥川賞作家として数多くの作品を発表してきた岡松和夫が60歳をこえてから発表した作品である。しかも登場人物が誰なのか容易に推察できる。真実を語ろうとする岡松和夫の覚悟を感じると同時に、荷風の行き過ぎた筆誅のせいで不名誉をきせられた平井の無念をはらしてあげたい、荷風の視点でのみ罵倒されてきた事件に冷静な光をあてたいという思いが伝わってくる。
荷風「来訪者」を読んでも、岡松和夫「断弦」を読んでも、 平井呈一 の印象はとても穏やかな、博識な人物ということで揺るぎない。
小千谷に疎開中、年頃の娘たちとともに妻妾同居の状態になりながら、娘も、妻も素直にその状態を受け入れ、のんびりとしている様子が意外であった。これも平井の人柄からだろうか。また稼ぐことは苦手な平井ながら、妻が入院すれば入院費をかせぐために働く……と誠意をみせ、愛人のほうも控えめに過ごしたから紛糾しなかったのではないだろうか?
また疎開先の小千谷で平井が勤務した学校でも、いかにも平井らしい穏やかな勤務ぶりが伝わってきて興味深い。
「来訪者」や「断弦」を読んで感じることは、多少の描写の違いはあるにしても、荷風は「穴のあなが小さい」ということである。平井の経済状況を助けようとする考えは毛頭なく、「来訪者」でむしろその困窮ぶり、下町ぶりを揶揄するような文を残した荷風。妻妾子同居だけれど仲睦まじい家庭について、勝手な思い込みで情痴の世界を描く文を残した荷風。やはり荷風は、穴のあなが小さい。
これから「断月」に書かれている荷葉との蜜月時代から、その決別後まで白井の胸中がうかがえる文を以下にいくつか青字で抜き出しておく。
もともと良家の子弟であったことにくわえて、作品の成功で豊かだったにもかかわらず、自分を慕ってきた白井の経済的窮状に対して、荷葉がいささかの思いやりもく、仕事を考えて弟子を助けようとする思いもなく……。かたや平井は荷葉にご馳走にならないように気をつかいながらお供、その姿はなんともいじらしい。
荷葉が銀座や浅草に出かける時には一緒に行くことも多い。食事を共に摂ることがある。荷葉が今夜はこれこれのことをしてもらった御礼だからと言わない限り、食事代は自分で払うように心掛けた。(「断弦」94頁)
翻訳が収入にはならず、妻も病気になって経済的に困った白井は、荷葉の色紙を真似て知り合いの古本屋に売る。荷葉にいれこんだ白井には自分の窮状を荷葉に相談することもできない。白井はいずれ荷葉の耳にはいることも覚悟する。やがて荷葉から自分の偽筆がでまわっている話を聞かされた白井は打ち明ける。
「『紫陽花』の原稿というのだがね。それが、よくできているらしい。そっくりの字らしいよ」などと話した。
「それはきっとわたくしのものです」
貞吉は言葉をすらすらと口にできたのが嬉しかったほどだ。貞吉は色紙や短冊のことも話した。
荷葉は驚いたようだった。
貞吉はさすがに頭を下げて荷葉の言葉を待った。荷葉が家から出ていくように言えば、すぐ立ち上がるつもりだった。金に困ってなどと言訳がましいことは口にしたくなかった。
「白井さん、日本橋で食事して、一緒に浅草に行ってみましょうや」
荷葉は何も聞かなかったように、そう言って客間の椅子から立ち上がった。
貞吉はすぐには声が出なかった。自分は許されているのか、そんなことはよく分からなかった。ただ、慄えがくる程に嬉しかった。 (「断弦」110頁)
偽筆事件が発覚してから六年間、荷葉はとくに何も言うこともなく、白井とつきあいを続けたようである。
それが1941年12月20日になって荷葉の態度は豹変する。ちなみに其の13日前の1941年12月7日に日本は真珠湾を攻撃、日米が戦うことになる。荷風の日記、断腸亭日常にも開戦と共に逼迫していく世相が克明に記されている。
ようやく翌日の夜、麻布の家を訪ねていって、荷葉の応対の随分変わってしまったのが、はっきりと分かった。
貞吉が何を話しても、荷葉が愛想よく笑うことはなかった。貞吉は何がこう荷葉を変えてしまったのか分からなかった。偽筆した原稿や書が原因というのなら、もっと早く絶交を言い渡されてもよかったような気がした。百円を借りたまま返さないこともあるのだろうか。まさか。貞吉は事情の呑みこめないまま三、四十分で辞去した。こんなことは初めての経験だった。 (「断弦」129頁)
荷葉から白井との交渉をたのまれた元文学青年石津は、荷葉の変貌を以下のように語る。でも「白井さんは荷葉にとって疫病神のようになりかけている」という石津の言葉は、かなり真実を言い当てているのではないだろうか?
あざとい荷風は日米開戦後の厳しくなりゆく社会をすばやく察知、自分の平和をかき乱す疫病神として白井を判断したのかもしれない。そうだとすれば白井のどこが疫病神に思えたのだろうか?
荷葉の痴情をつづった私信や四畳半襖の下張の流出への恐怖、愛人のいる白井の私生活への恐怖、敵国の言葉を翻訳している白井の生業への恐怖。厳しくなりゆく世相への恐怖。
荷葉の胸中で恐怖が幾重にも重なっているのに、白井は仙人のように呑気で金銭面でもあいかわらず。そうした無防備な白井の言動に刺激され、爆発してしまったとも、厳しくなる社会から巧みに距離をとろうとしたようにも思える。
私は電話で話しただけですが、荷葉さんは変りかけていますよ。私生活でも今迄のような放蕩はもう危ないと思っているようです。若い私がこんなことを言うのはおこがましいのですが、白井さんは荷葉さんに心酔していた。荷葉さんは白井さんの文学的才能を認めていた。生活に困った白井さんが偽作を作っても、それを面白がるようなところがありました。しかし、その偽作のなかには四畳半襖の下張のような危険な艶本もある。あれを読んだ人は皆写していますよ。もし警察があれを調べ出したら、どうなりますか。こんな時代になって、白井さんは荷葉にとって疫病神のようになりかけているのです。
それにしても確かに金を貸したとはいえ、縁を切ると同時に、かつて親しく浅草を歩いていた白井に、その百円の借金証文を差し出すように請求してくるとはあまりに狭量な仕打ちではないだろうか?
(途中略)それから暫くして予想していたように荷葉からの手紙が届いた。石津に教えた通り「本所区石原町一ノ五二稲村竹之助方」と所番地が記されていた。貞吉は絶交状だと思っていたが、手紙には百円返済の要求と、すぐに返せない時には連帯保証人をつけて借金証文を差し出すようにと書いてあった。(「断弦」132頁)
「来訪者」を読んだ白井は、たしかに「薄っぺらに描かれている自分」を発見し、「役に立つ間の付合」にすぎなかったと思ったことだろう。
しかし、小説のなかの青年文士と自分とは、まるで違っている。一方で、世間では当然モデルと思い込む。こんな薄っぺらな姿に描かれたことが悔しかった。この作品のなかの青年文士のようであれば、何のために文学の道に執着してきたのか分からなかった。 (「断弦」176頁)
こちらとしては一生のなかでも教わることの多い何年かだったから。偽筆などは荷葉さんも面白がっていたんだよ。放蕩無頼ではあっても、反俗の文学精神だけは共有していると思っていた。しかし、荷葉さんにとっちゃあ、役に立つ間の付合だったのかしらね。 (「断弦」181頁)
一連のやりとりを荷風側、平井側から両方から眺めてみたとき、荷風の狭量さ、あざとい振る舞いを強く感じずにはいられない。
その狭量さを思うとき、荷風だけが「来訪者」で残している「平井は鏡花に私淑しているのか」という言葉も非常に気になる。
もしかしたら荷風と雑談をしているとき、平井は無邪気に鏡花への賛美の念をあらわしたことがあったのではないだろうか?そうだとすれば、相手は狭量な荷風である。その言葉は自分への限りない侮辱に思えてしまい、数々の不安を爆発させる契機にも、しつこい筆誅小説を書こうとする動機にもなったのではないだろうか?
あとから平井も荷風のそうした思いに気がついたのでは? でも何かを言い返して荷風との泥仕合になるような愚かな道は、マイナー・ポエットの矜持がある平井呈一としては選びたくなかったのではないだろうか……そんなことを考えつつ頁を閉じる。
2019.03.13読了