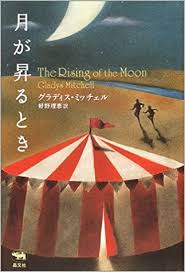少しだけ驚いて、マイケルは立ち上がると、もったいぶってお辞儀をしてから、再び腰をおろした。
「こうした人々は、パーシィ師の説教のあいだ、沈黙していないにしても、承認の拍手くらいはしました。師は話の程度を相手にあわせて引き下げ、機知に富んだ警告を用いながら、土地の賃貸料のことやら労働をしないですますことについて話しをされました。私有財産の没収や土地の収用、調停など私の唇を汚さないではいられないような会話が延々くりひろげられたのです。数時間後に嵐がおきました。私は、その集まりでしばらく説教をして、労働者階級には倹約精神が欠け、晩の礼拝への参加する者があまりいないこと、感謝祭も無視する者がいること、その他にもたくさん人々を物質面で助け、改善の手をさしのべるようなことについて話をしました。
With a slight start, Michael rose to his feet, bowed solemnly, and sat down again.
“These persons, if not silent, were at least applausive during the speech of Mr. Percy. He descended to their level with witticisms about rent and a reserve of labour. Confiscation, expropriation, arbitration, and such words with which I cannot soil my lips, recurred constantly. Some hours afterward the storm broke. I had been addressing the meeting for some time, pointing out the lack of thrift in the working classes, their insufficient attendance at evening service, their neglect of the Harvest Festival, and of many other things that might materially help them to improve their lot.