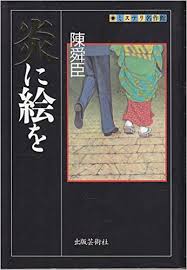「スミスが略奪者として現れる事件はすべて」アメリカ人の博士は続けた。「押込み強盗の事件です。前の事件と同じような事件の過程を追いかけながら、その他の事件から、私たちは明らかな例を選びます。そうすれば一番ただしくて、疑う余地のない証拠を手に入れることでしょう。これから私の同僚のグールド氏に頼むつもりですが、真面目で、潔白な、ダーラムの聖堂参事会員、ホーキンス聖堂参事会員から受けとった一通の手紙を読んでもらいましょう」
モーゼス・グールド氏はいつもの俊敏さで跳びはね、真面目で、汚点のないホーキンスからの手紙を読もうとした。モーゼス・グールドは田舎の庭にいる雰囲気を上手に真似た。サー・ヘンリー・アーヴィングには遠くおよばないが、マリー・ロイドにはかなり近づいている。新しい自動車の警笛を真似る様子は、芸術家たちの殿堂いりをするほどだ。
“All the cases in which Smith has figured as an expropriator,” continued the American doctor, “are cases of burglary. Pursuing the same course as in the previous case, we select the indubitable instance from the rest, and we take the most correct cast-iron evidence. I will now call on my colleague, Mr. Gould, to read a letter we have received from the earnest, unspotted Canon of Durham, Canon Hawkins.”
Mr. Moses Gould leapt up with his usual alacrity to read the letter from the earnest and unspotted Hawkins. Moses Gould could imitate a farmyard well, Sir Henry Irving not so well, Marie Lloyd to a point of excellence, and the new motor horns in a manner that put him upon the platform of great artists.