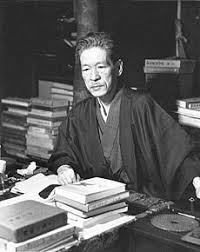「怪盗ニック全仕事1」

著者:エドワード・D・ホック
訳者:木村二郎
創元推理文庫
価値のないものに限って盗む怪盗ニック。
どうやって盗むのか、なぜ盗みたいのか、ひとつひとつひねりの利いた話が楽しい。
木村氏の訳も読みやすく、怪盗ニックの話を堪能。
ただ今週末の読書会の課題本なので、時間つぶしになりそうな些細な疑問を少々。
英文はエドワード・D・ホックの原文から、訳文はすべて創元推理文庫「怪盗ニック全仕事1」木村二郎氏の訳文より。
*斑の虎を盗め
・「そこは眠るためと愛し合うためにあるんだから」
They’re only for sleeping and making love.
―原文は、ここまでハードボイルド調だろうか?
・「確信のなさそうな口調だった」
The voice asked, uncertain.
―確信のなさそうという意味なのか?
・「涼しい夜もあるのだ」
He picked up his jacket on the way out the door. Sometimes the nights were cool.
―原文には、ここまで強い意味があるのだろうか?
・「生温いスコッチ」
Warm scotch
―酒をのまないので分かりませんが、スコッチに冷えてる、生温かいがあるのでしょうか?
・「でもこんなにハンサムだとは思ってもみなかったわ』
ニックは自分が二枚目ではないことがよくわかっていた。」彼女の脚を見るのをやめ、心の中で心配しはじめた。
But I never thought you’d be so handsome.
Nick was no matinee idol and he knew it. He stopped looking at her legs and started to worry.
―原文では下線と前の文と下線のつながりが分かるが、日本語になると分かりにくい気が。前後の文をつなぐ一語が訳にあると、私にも分かりやすいのかも。
・「コーミックまではひとっ飛びだった。うしろで、スミスが叫び始めた。
そのあと、ニックはトランキライザー銃を虎に向けて撃ってから」
The tiger leaped for the lighted trailer and made it to Cormik in a single bound. Behind him, Harry Smith started to scream.
Afterward, Nick used the tranquilizer gun on the tiger
・himを訳したほうが恐怖がじわじわ増してくるのでは? 原文では、Afterwardの文との間に怖いマがあるのだが、日本語にはない気がする。
*プールの水を盗め
・「わたしのプールの水はどうなるんだ?」
What about my pool?
―水とまでは言っていないですが。水と訳すとケチくさいような気も。プールをどうしてくれるんだ位の意味では?
・「水の干上がった小川があるの」
We can dam it up and keep it there.
-小川だと流れていってしまうのにと思いましたが、原文ではdam up 、「ダムをつくってせきとめる」が正確なのでは?
・「あなたのプールの水には塩素が含まれているわ。塩素が石灰セメントに及ぼす作用をご存じないようね。きっとあの水からわずかなカルシウムが検出されるのよ、サム。十年たった今でもね」
There’s chlorine in your pool water. Apparently you’re not familiar with the effects of chlorine on calcified cement. There’ll be traces of calcium in that water, Sam, especially after ten years.
―traces of calciumが「わずかなカルシウム」だとtraces の不気味さが欠けてしまうのでは?
*邪悪な劇場チケットを盗め
・タイトルですが、The theft of the wicked tickets のwicked は邪悪の方がよいのか、本文中で処理しているようにウィッキドとカタカナ表記の方がいいのか?
・「雨が小降りになったところで、数軒むこうの戸口に移った。政治集会のポスターが風で吹き飛ばされ、縁石脇の水たまりにはまるのが見えた。そして、ポスターのインクがだんだん水を染めていくのに気がついた。屋外用のポスターにしては、あまりよくない印刷だなと思った。
それから少したって、雨はまだ土砂降りになった。ニックはなんとかタクシーを拾い、ギリニッジ・ヴィレッジへ向かった」
Nick moved a few doors up the street during a temporary lull in the downpour. He watched a poster for some political rally swept away by the wind until it settled into a curbside puddle, then noticed the ink from it gradually discovering the water. Not very good printing for an outdoor sign, he thought.
Shortly afterward, the rain pelting again, he managed to catch a taxi and headed for Greenwich Village to seek out the off-Broadway theater where Bill Fane was rehearsing his new play.
―ここでニックは閃いて、ハッとして行動するのですよね? 「それから少したって」という訳だと、閃いたという感じがでないのでは?
*囚人のカレンダーを盗め
・タイトルがThe Theft of the Convict’s Calendar と The Theft of the Coco loot の二種類あるようですが、もとはどちら?
・最後の場面も少し変わっているようです。どちらが新しいものか気になります。
「意図を汲み取った」と訳すとマッジが善意のひとになってしまわないでしょうか?
「でも宝石が…」
ニックはずっと笑みを浮かべていた。手の拳銃と脇下のライフルの銃口はさりげなく地面のほうを向いていたが、マッジは彼の意図を汲み取った。「おれが預かっておく。クロフトは手数料の残りを払ってくれてないからな」
「でも…」
「さあ、行くぞ。宝石はおれがしばらく預かって、ながめさせてもらおう。それから、所有者に返すかもしれない」ニックはしばらく考えてから、付け加えた。「たぶんね」
”But the jewels-“
Nick kept on smiling, and the gun in his hand and the rifles under his arm were casually pointed at the ground; but she got his message, “I’m keeping them. Croft never paid me the balance of my fee.”
*青い回転木馬を盗め
―回転木馬の真鍮の輪、見たことがないので情景がうかんできません。表紙かどこかに回転木馬の真鍮の輪の絵がほしいです。
・「デフォーが腕木を伸ばした木製の真鍮の輪ディスペンサーを見あげた。「今は空っぽだな」と言った。「真鍮の輪はもうないよ」木馬に乗ったまま、横に伸びた腕木の先のディスペンサーから運よく真鍮の輪を取れたら、無料でもう一度乗れるのだ。
ニックは盗まれた二体の木馬があった場所から目を離さずに、うなずいた。たぶん、デフォーにとっては、真鍮の輪はこれからもずっとないのかもしれない。」
Dan Defoe glanced up at the wooden hopper with its outstretched arm. “The thing’s empty,” he said. “No brass rings any more this year.”
Nick nodded, his eyes on the spot where the two stolen horses had been. Perhaps, for Dan Defoe, there would be no brass rings any more, ever.
―情景がうかびません。版が違うのかもしれませんが。
・「ニックは木の下に車をとめ、ヘッドライトを消した。青い木馬が待っているのが見えたが、もう少し長く待たせておく必要がある。メリーゴラーラウンドのシャッターがあいた側面は灯台のように光っていたので、その光が何を招き寄せているのか見てみたかった。」
Nick parked his car under a tree and put out the lights. He could see the blue horse waiting, but it would have to wait a little longer. The merry-go-round’s open side was like a lighthouse beacon, and he wanted to see what that beacon might attract.
―木馬を主語にして訳すと、少し不自然な文のような気もしますが。そこが面白い文なのでしょうか?
―光の箇所も微妙にニュアンスが原文と違う気もしますが。「招き」という言葉のせいでしょうか?
・「彼は五分の猶予をみて、車が戻ってこないことを確かめた。そのあと、行動に移った。メリーゴーラウンドの明かりを消し、道具の一緒に持ち歩いている電池式小型ランプをつけた。そして青い木馬の胴体を縦に貫く真鍮のボルトを素早く外した。その真鍮棒はメリーゴーラウンドの天井と床にはまっていて、木馬が駆ける動作に生気を与えている。メリーゴーラウンドは複雑な機械だが、同時に単純でもある。木馬をノコギリで切って破損させる必要などはない。一体の木馬を盗んでもらうためにニックを雇ったピーター・ファウルズは、損傷なく受け取ることができるだろう。
何層ものペイント層のせいで真鍮棒がなかなか外れず、」
He gave them five minutes to make certain their car would not return. Then he set to work. He doused the lights in the merry-go-round and set up a small battery-operated lamp that he carried with his tools. Then he quickly unbolted the brass pole which ran up through the center of the blue horse, attaching it to the carousel proper and giving life to its galloping motion. A merry-go-round is a complex piece of machinery, and yet so simple. There was no need to saw through the wooden horse and thus destroy it. Peter Fowles was payng Nick for one horse and he would have it, all in a single piece.
The layers of paint made the brass pole stick,
―the carousel とは?
―「一体の…」、語順のせいか分かりにくい気が。
―「損傷なく」という解釈でいいだろうか?
―「何層ものペイント層」?意味は分かるのですが…。
・「メリーゴーランドの床の下に放り込んだのか?」
Did he slide them under the merry-go-round?
―なんと訳せばいいのでしょうか? やはり床の下?
・「ニックは包みを二人の頭越しに放り、ふたのない真鍮の輪入れの中に投げ込んだ」
Nick threw the package over their heads, straight into the open hopper that was supposed to hold the brass rings
―open hopper とは?真鍮の輪入れがある回転木馬体験がない身には思い浮かべるのが難しい。
・「少なくとも、ニックは最後の運搬物を組織のボスのもとに届けるべきだと考えた。回収の手数料を少しいただくかもしれない。グロリアの指輪にしたら似合いそうな、素敵な青白いダイヤモンドがあったのだ」
But at least Nick felt he should deliver this last shipment to the man. Perhaps he’d take a little commission for himself. There was a fine blue-white stone that would look perfect in a ring for Gloria.
―「少しいただくかもしれない」という控えめなニュアンスか?
読了日:2017年8月14日