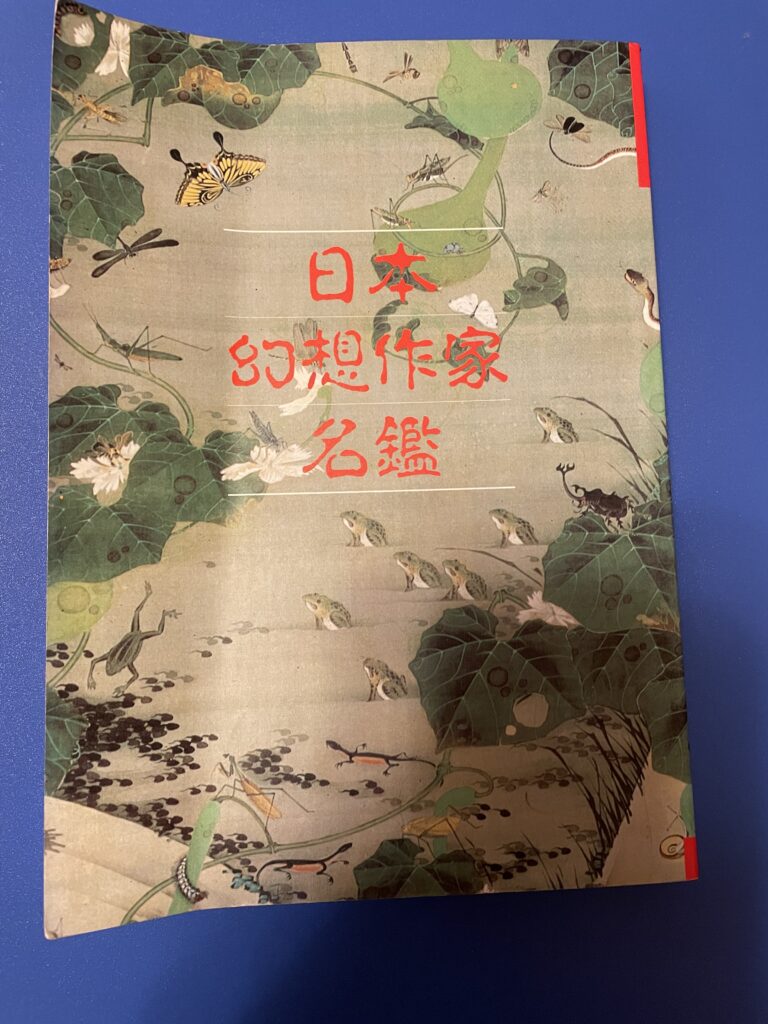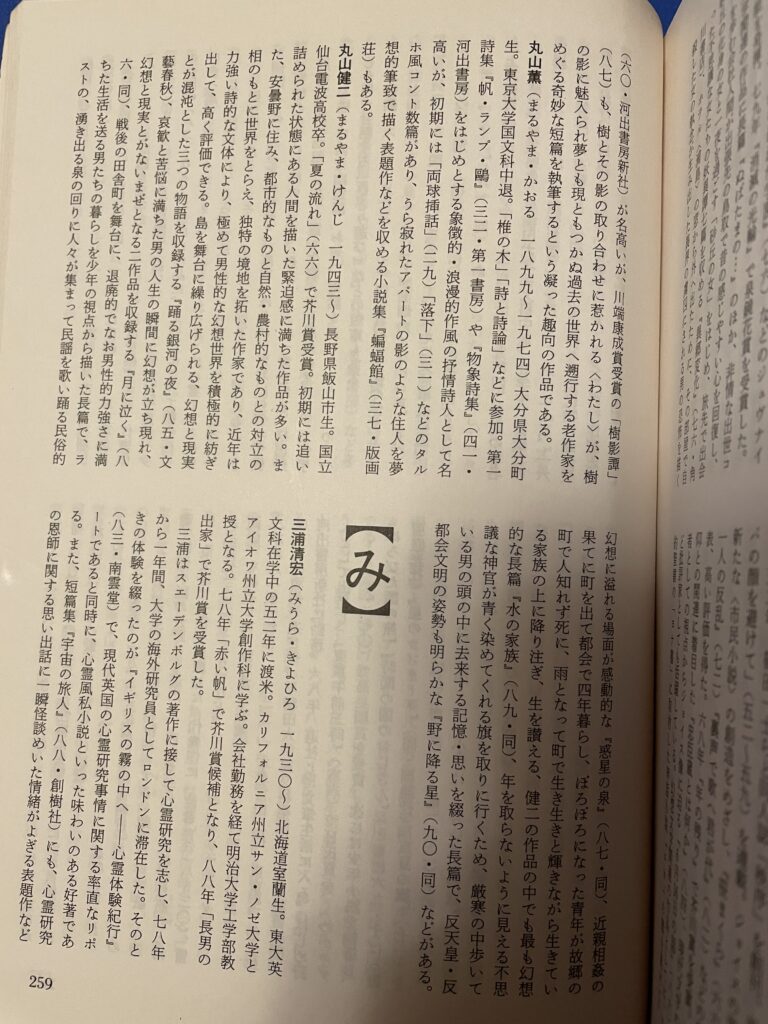ロアンの名前の響きの良さに惹かれて小沢蘆庵の歌を一首鑑賞する

昨日、西崎憲氏が制作された奥村晃作氏が短歌について語るドキュメンタリー動画を視聴していたら、「ロアン」なる昔の歌人の名前が頻出。
歌のことはまったく知らない私は、「ロアン」なんてすごく響きのいい名前!と印象に残り、動画終了後さっそく調べてみる。「ロアン」とは江戸時代の歌人「小沢蘆庵」のことらしい。
以下、日本百科全書の「小沢蘆庵」の説明より引用。
江戸中期の歌人。名は玄仲 (はるなか) 、通称は帯刀 (たてわき) 。観荷堂と号する。父はもと大和宇陀 (やまとうだ) (奈良県)の藩主織田 (おだ) 家に仕えた小沢喜八郎実郡(実邦)(さねくに) 。大坂で育ち、尾張 (おわり) 藩成瀬家(また竹腰家)の京都留守居役本庄勝命(ほんじょうかつな) の養子となり本庄七郎と称した。30歳ごろ冷泉為村 (れいぜいためむら) に入門して歌道を学んだが、51歳ごろ破門される。35歳ごろ小沢氏に復姓。このころから鷹司輔平 (たかつかさすけひら) に仕えたが、1765年(明和2)43歳のときに出仕を止められ、その後は歌道に専念する。享和 (きょうわ) 元年7月11日没。寛政 (かんせい) 期(1789~1801)京都地下 (じげ) 歌人四天王の一人に数えられ、伴蒿蹊 (ばんこうけい) 、上田秋成(あきなり) 、本居宣長 (もとおりのりなが) などと親交があった。門人には妙法院宮真仁(しんにん) 法親王をはじめ小川布淑 (ふしゅく) 、前波黙軒 (まえばもくけん) 、橋本経亮(つねあきら) など多くの歌人がある。歌は心情を自然のまま技巧を凝らさずに詠出すべきであるとする「ただこと歌」の説を提唱する。これが、教えを受けた香川景樹 (かげき) などによって、江戸後期の京坂地下歌壇の主流となる。家集に『六帖詠草 (ろくじょうえいそう) 』がある。歌論書に『ちりひぢ』『振分髪 (ふりわけがみ) 』『布留 (ふる) の中道 (なかみち) 』がある。古典和歌の研究にも熱心で、多くの歌書の写本を所蔵していた。
(日本百科全書)
ちなみに小沢蘆庵が唱えていた「ただごとの歌」は、日本国大辞典には以下のように説明があった。
「古今集」仮名序に示された歌の六義(りくぎ)の一つ。真名序の「雅(が)」に当たり、「ただごと」は正言の義で、雅の直訳。のちに、物にたとえていわないで直接に表現する歌、深い心を平淡に詠む歌と解され、小沢蘆庵の歌論の中心になる。(日本国語大辞典)
「魯庵」という名前の響きといい、唱えたという「ただごとの歌」という言葉の響きといい、響きだけで気になる。
ただ、比喩とかを楽しみたい私には「ただごとの歌」の精神は方向性が違う気もするけれど。
とにかく、こんな素敵な響きの名前や言葉を思いついた魯庵の歌を見てみようと、ジャパンナレッジに収録されている新編 日本古典文学全集68巻「近世和歌集」の小沢魯庵の歌を見てみる。
歌
鶯はそこともいはず花にねて古巣の春や忘れはつらむ
意味
鶯は特に場所を定めるわけではなく次から次へと宿とすべき花を替えて、古巣で過ごした春のことをすっかり忘れているいるだろう。
解説
転居の多かった蘆庵のこと、あるいは自己像を重ねているのかもしれない。
語句解説
そこともいわず……特に場所を定めるわけではなく
(新編 日本古典文学全集68巻「近世和歌集」より)
ただごとの歌とは「物にたとえて言わないで直接に表現する」と唱えていたの割には、最初から「鶯」に自分自身を重ねている。
でも、この重ね方がなんとも可憐で風流である。
「日本の歳時記」によれば、「鶯」のことを「歌詠鳥」とも言うらしいから、たぶん蘆庵自身のことを言っているのだろう。
また鶯は季節によって住む場所を変える鳥だそうだ。
解説にあるように、転居の多かった蘆庵の人生を重ねているのかもしれないし、師に破門された自身の歌人人生を重ねているのかもしれない。
「花にねて」という言葉が飄々としてるから、破門された悲壮感がなく、少しだけ悲しみと諦念があって「忘れはつらむ」と自分に言い聞かせている気持ちに親近感を覚えた。