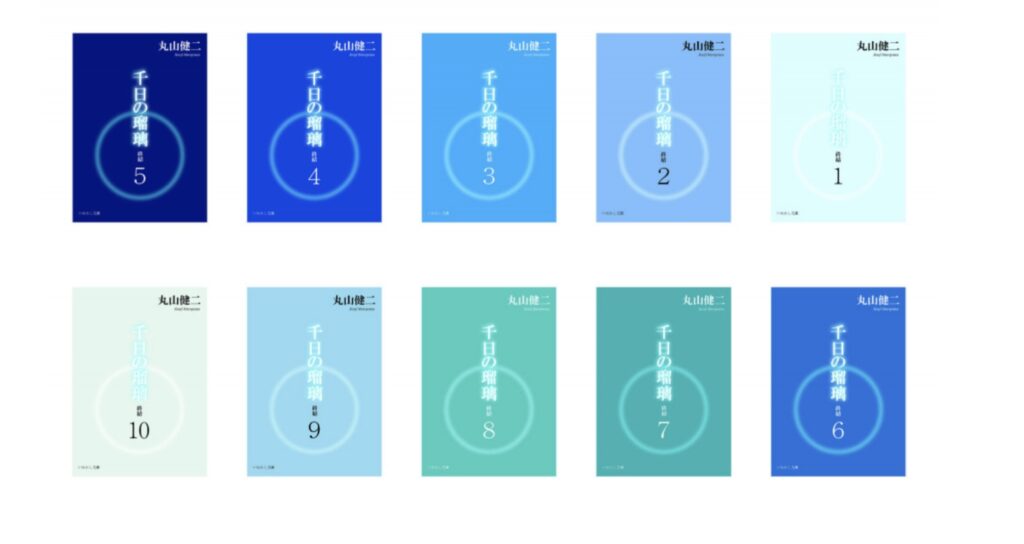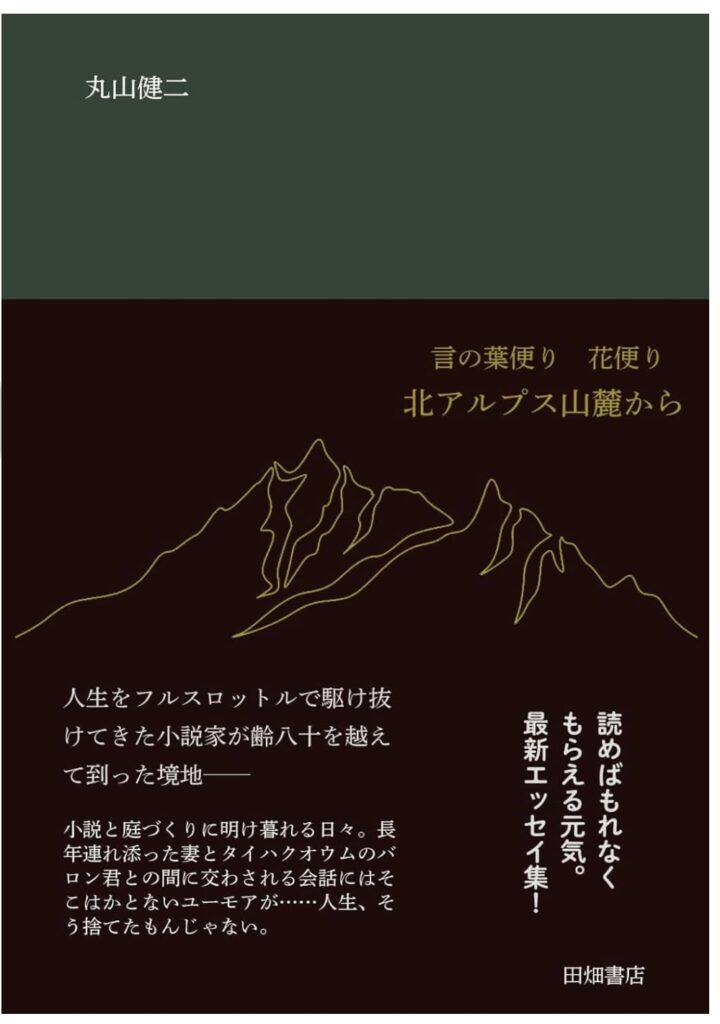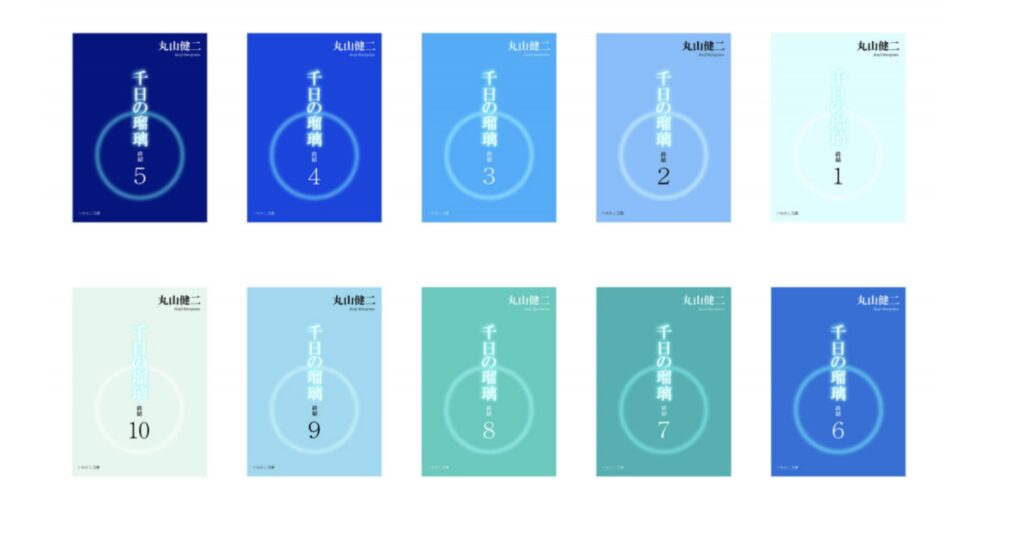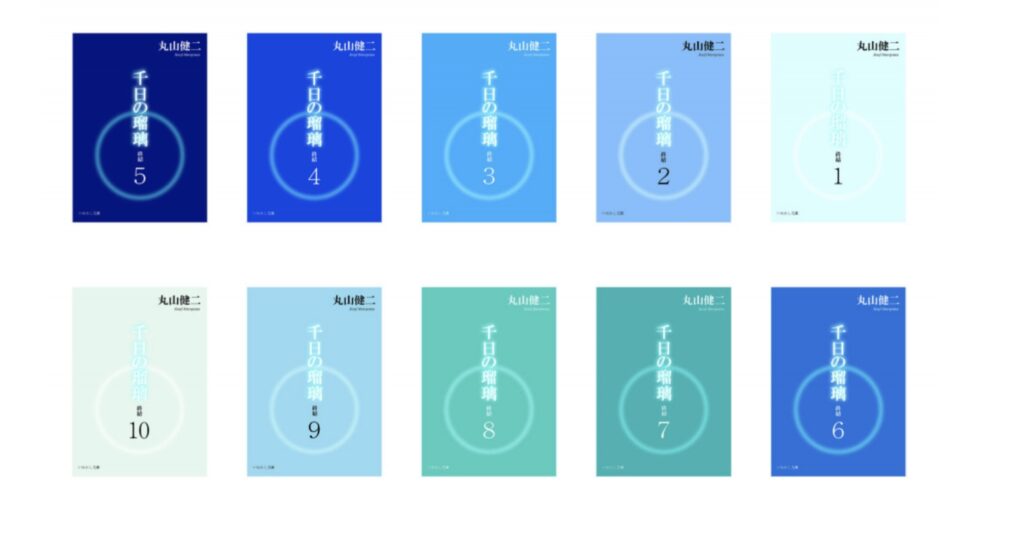丸山健二『千日の瑠璃 終結5』より十一月十八日「私は絶叫だ」を読む

十一月十八日は「私は絶叫だ」と「絶叫」が語る。誰からも気がつかれない絶叫であり、「一瞬息を止めても すぐに私を錯覚と見なし」てしまう絶叫である。
そういう不可思議な絶叫も、以下引用文も、どこか現実の一本向こうにある不思議な世界の趣きがある。丸山文学の魅力に、こうした幻想めいたところがあると思うのだが、初期作品にはあまりこうした感覚はなく、徹底的に現実を見据えている気がする。
作品にどんどん幻想めいた要素が入り込み変化していったせいで、初期の読者はついていけなかったかもしれない。また幻想文学ファンは、初期作品のイメージが強くて、あまり手に取ろうとしないのかもしれない。残念なことだと思う。
それでも私は
捨て身で敵陣を突破する兵士のように突っ走り
四囲の暗黒の山に撥ね返され
無人のボートが密かに死者の魂を運ぶ山上湖をさまようのだ。
丸山健二『千日の瑠璃 終結5』57ページ