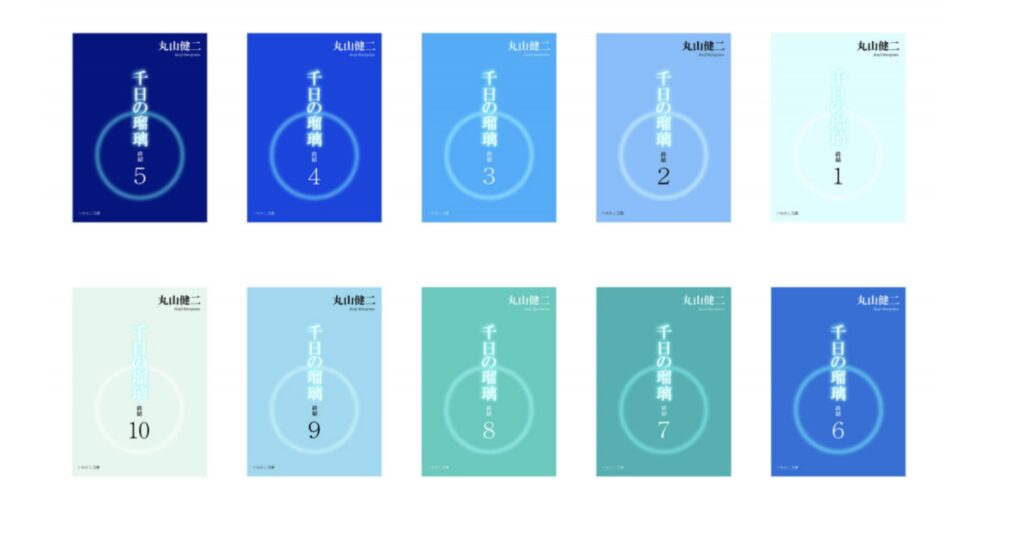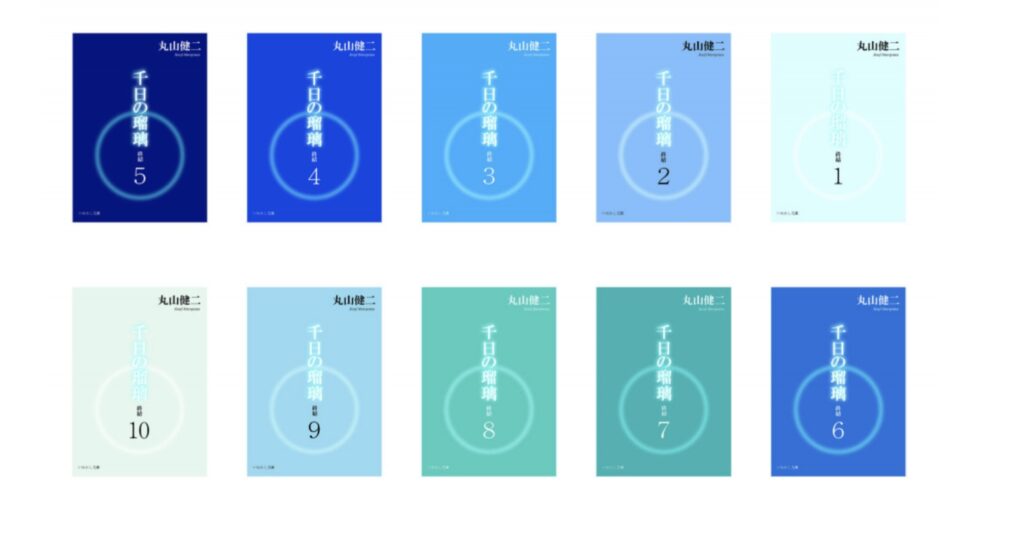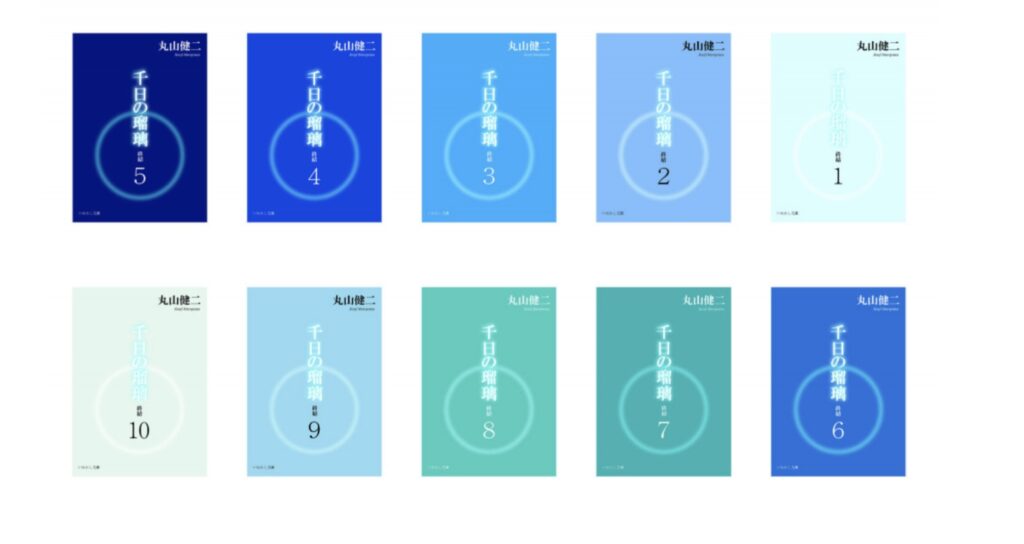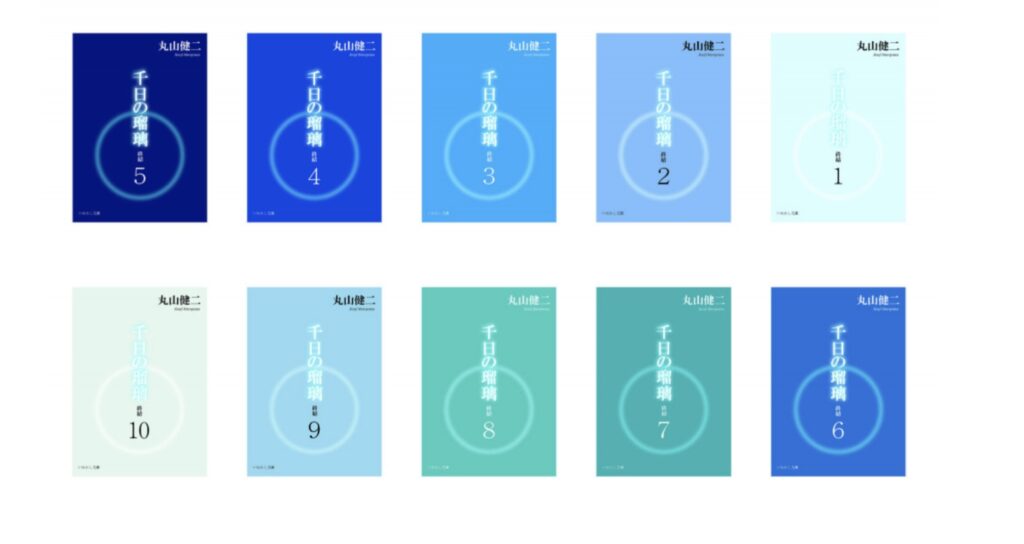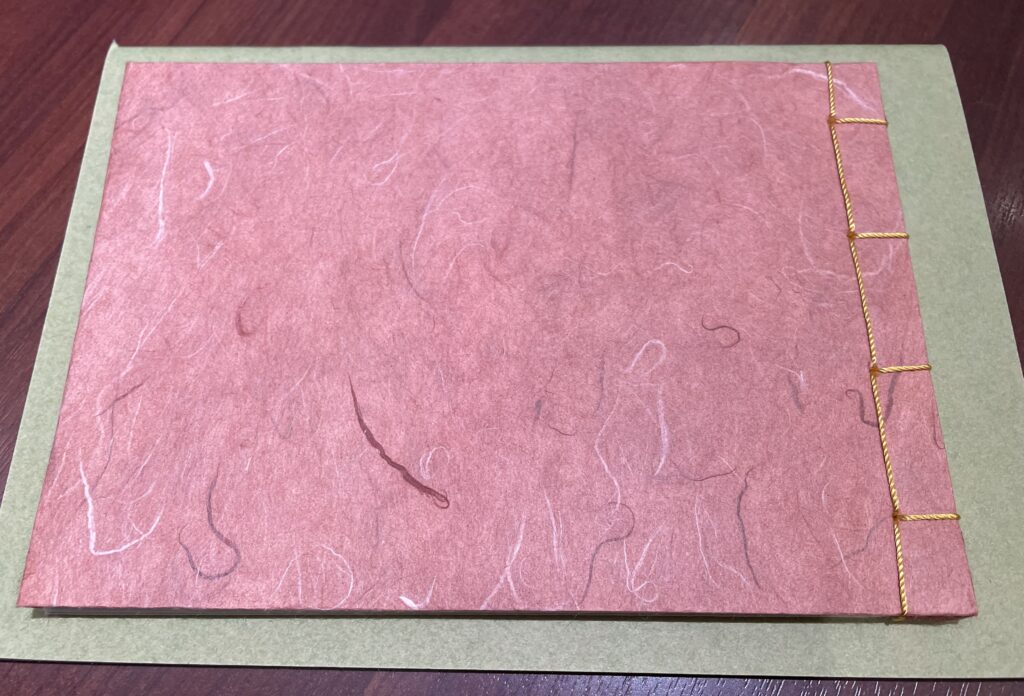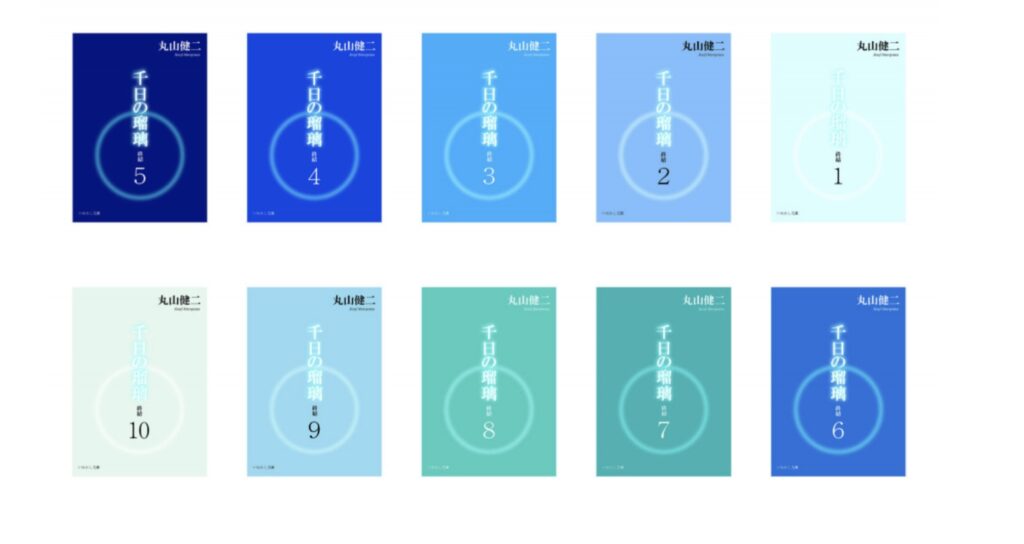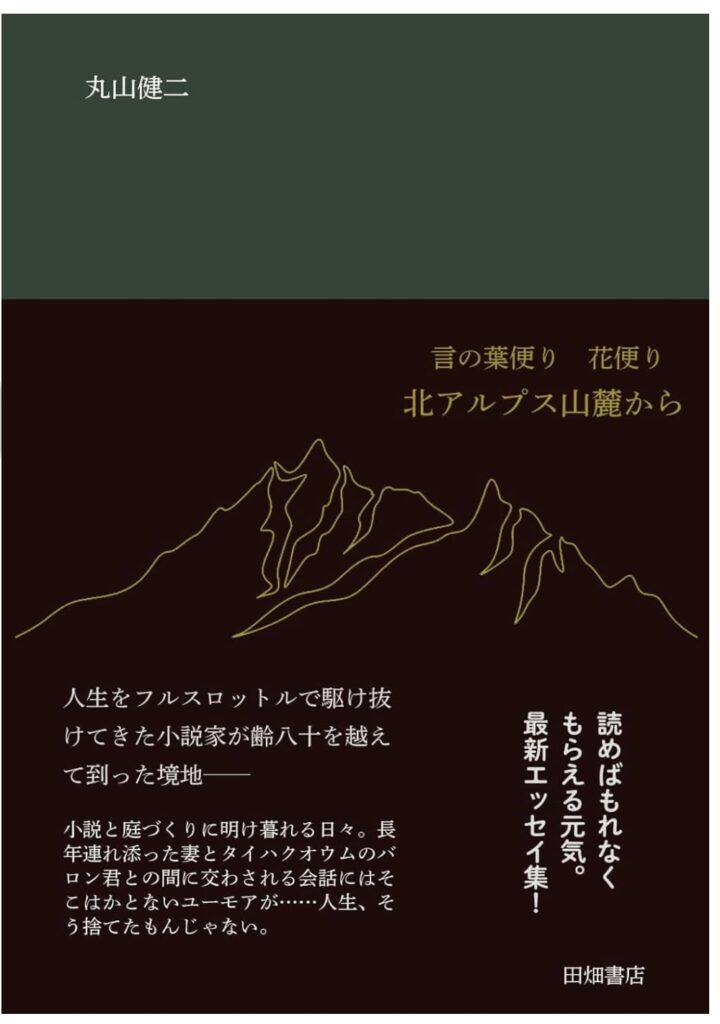丸山健二『千日の瑠璃 終結4』より十月二十九日「私は想起だ」を読む
十月二十九日は「私は想起だ」と、「少年世一のどこまでも不完全でありながら 同時に完全でもあり、 万事にあけすけな脳から次々に生まれる 変幻自在の想起」が語る。
以下引用文。
私たちの脳裡をとりとめもなく過ぎっていく想起の数々。
いったい何処から生まれるのだろう。過去の日々か現在の無意識か未来の予感、それとも別次元に存在している知らない私の記憶?
理解できていなかったり、意識になかったり、そのときには意味もなかった場面や言葉が浮かんでくる記憶の不思議さを思う。
たしかに「想起」こそ人間の証拠なのかなあと思う。
ときとして彼は
生まれてくる前にどこかで得た体験とどこかで仕入れた知識でもって
私を仰天させることがあり、
たとえば
笛や太鼓に囃されてひと差し舞った日々や
たとえば
立憲君主制の打倒に欠かせぬ言葉の数々が
突如として甦ることが間々あり、
それこそが
人間のなかの人間である
何よりの証拠なのだ。
(丸山健二『千日の瑠璃 終結4』375ページ)