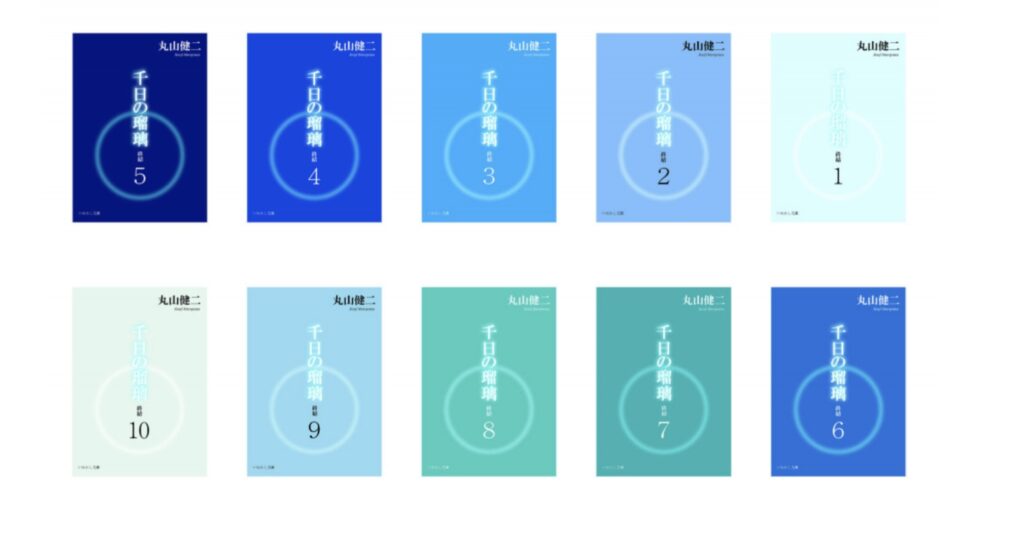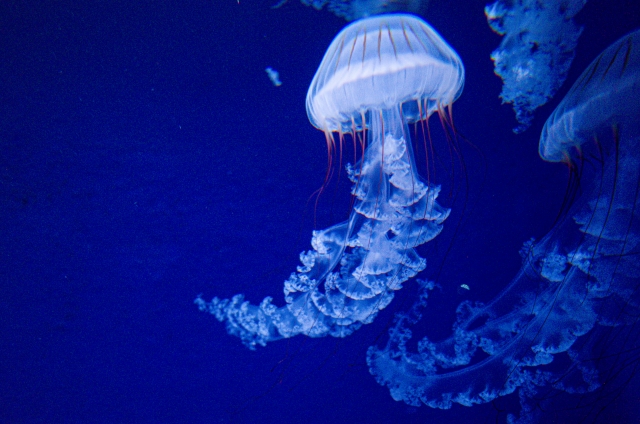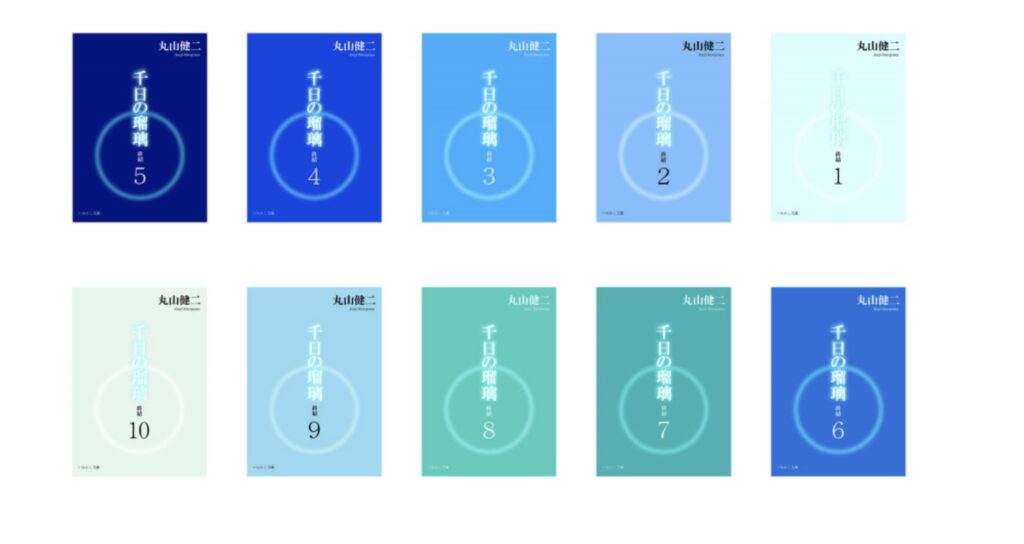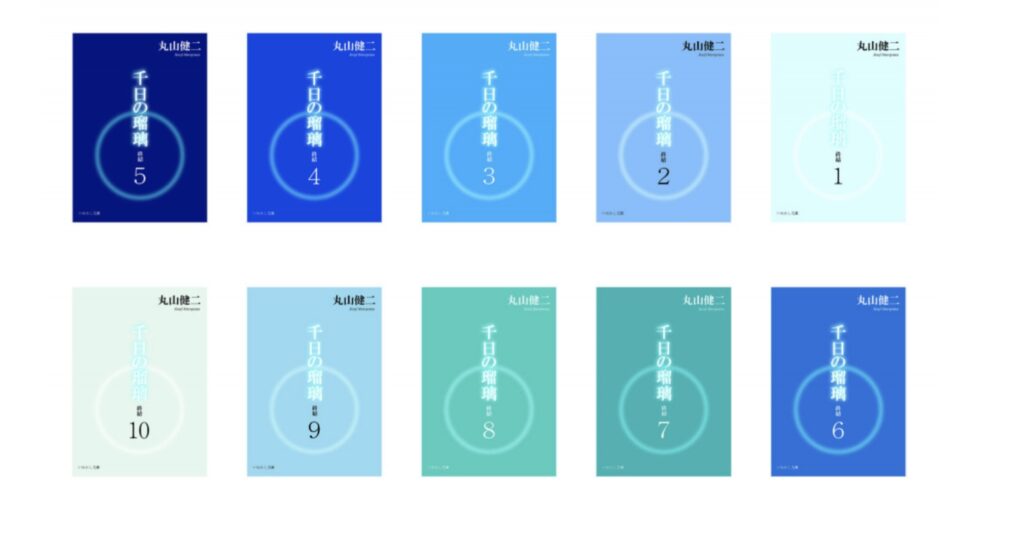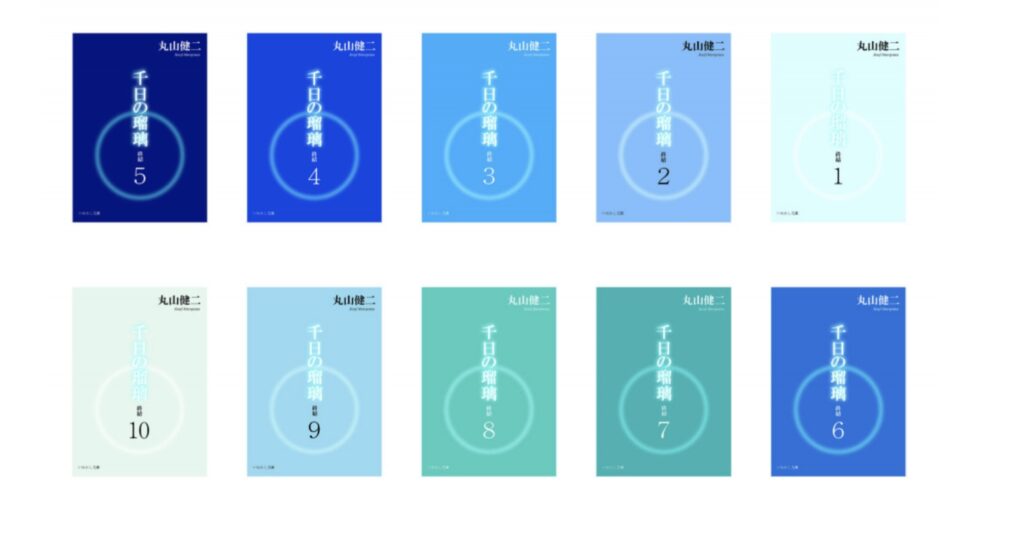福島泰樹短歌絶叫コンサートへ
ー「風に献ず」と「賢治幻想」の世界を楽しむー

福島泰樹短歌絶叫コンサートを聴きに吉祥寺のライブハウス曼荼羅に行ってきた。ぼーっと聴いていたから、間違いも多々あるかもしれないが、当てにならない記憶に残っていることを少しメモ。
毎月10日に開催されている短歌絶叫コンサートは、今年で40周年を迎えるそうである……。
今回ギターを演奏して歌ってくれた佐藤龍一さんと福島先生が最初に短歌絶叫コンサートを開いたのは、アテネ・フランセ……という場所も意外であった。
短歌絶叫コンサートをはじめたキッカケは、「当時は詩人が詩のコンサートをよく開いていた。でも短歌の歌といえば、宮中の歌会の節回しか牧水の歌のようなリズムしかなかった、短歌は歌謡なのに」という思いから始められた……と語られていた気がする。
短歌は短いから苦労もあったようだが、まず福島先生がコンサートの台本を書き、その台本を見て佐藤龍一さんたちが音楽を作り……。その逆の場合もあるそうだ。
それにしても40年、1200くらいのステージをこなしてきたとは凄いなあと思う。
今回は、まず岸上大作の歌を歌い、福島先生の第一歌集「バリケード1966年2月」を歌いながら、「詩の使命とは、文学の使命とは次の世代に伝えていくこと」と語る。
そして「学生たちがこれほど熱意をこめて社会を変えようとした時代があったのに、72年の連合赤軍から流れが変わってしまい、そうした動きを避けるように、語らないようになってきてしまった」とも嘆かれる。
たしかにこれだけの学生たちの熱量が蒸発してしまった背景……もっと知らなくてはとも思った。
福島先生が中原中也の「別離」について、「こんなにいい詩なのにあまり知られず論評もされていない」と残念そうに言われていた気がする。「別離」は短歌絶叫コンサートではしょっちゅう歌われるから、とても有名な詩なのかと思い込んでいた。
佐藤龍一さんの詩「合わせ鏡」も、合わせ鏡に合わせたようなイメージが次々と繰り出される詩で、こんな風にイメージが膨らませられるのかと驚いた。
私が今書いている長文でも、実は合わせ鏡のイメージを使っているのだが、こんなに展開していない……と反省することしきり。
もう今からでは遅いし。でも「合わせ鏡」ってイメージを刺激する存在だよね、と思いついた自分を褒めて納得する。
以前も引用したと思うが、中原中也の別離を以下に。
この詩は聞くたびに印象が変わる。
朗読者が何に別離を言おうとしているのかで印象が変わるのかもしれない。
別離
中原中也
1
さよなら、さよなら!
いろいろお世話になりました
いろいろお世話になりましたねえ
いろいろお世話になりました
さよなら、さよなら!
こんなに良いお天気の日に
お別れしてゆくのかと思ふとほんとに辛い
こんなに良いお天気の日に
さよなら、さよなら!
僕、午睡の夢から覚めてみると
みなさん家を空けておいでだつた
あの時を妙に思ひ出します
さよなら、さよなら!
そして明日の今頃は
長の年月見馴れてる
故郷の土をば見てゐるのです
さよなら、さよなら!
あなたはそんなにパラソルを振る
僕にはあんまり眩しいのです
あなたはそんなにパラソルを振る
さよなら、さよなら!
さよなら、さよなら!
2
僕、午睡から覚めてみると、
みなさん、家を空けてをられた
あの時を、妙に、思ひ出します
日向ぼつこをしながらに、
爪摘んだ時のことも思ひ出します、
みんな、みんな、思ひ出します
芝庭のことも、思ひ出します
薄い陽の、物音のない昼下り
あの日、栗を食べたことも、思ひ出します
干された飯櫃がよく乾き
裏山に、烏が呑気に啼いてゐた
あゝ、あのときのこと、あのときのこと……
僕はなんでも思ひ出します
僕はなんでも思ひ出します
でも、わけて思ひ出すことは
わけても思ひ出すことは……
――いいえ、もうもう云へません
決して、それは、云はないでせう
3
忘れがたない、虹と花
忘れがたない、虹と花
虹と花、虹と花
どこにまぎれてゆくのやら
どこにまぎれてゆくのやら
(そんなこと、考へるの馬鹿)
その手、その脣、その唇の、
いつかは、消えてゆくでせう
(霙とおんなじことですよ)
あなたは下を、向いてゐる
向いてゐる、向いてゐる
さも殊勝らしく向いてゐる
いいえ、かういつたからといつて
なにも、怒つてゐるわけではないのです、
怒つてゐるわけではないのです
忘れがたない虹と花、
虹と花、虹と花、
(霙とおんなじことですよ)
4
何か、僕に、食べさして下さい。
何か、僕に、食べさして下さい。
きんとんでもよい、何でもよい、
何か、僕に食べさして下さい!
いいえ、これは、僕の無理だ、
こんなに、野道を歩いてゐながら
野道に、食物、ありはしない。
ありません、ありはしません!
5
向ふに、水車が、見えてゐます、
苔むした、小屋の傍、
ではもう、此処からお帰りなさい、お帰りなさい
僕は一人で、行けます、行けます、
僕は、何を云つてるのでせう
いいえ、僕とて文明人らしく
もつと、他の話も、すれば出来た
いいえ、やつぱり、出来ません出来ません。