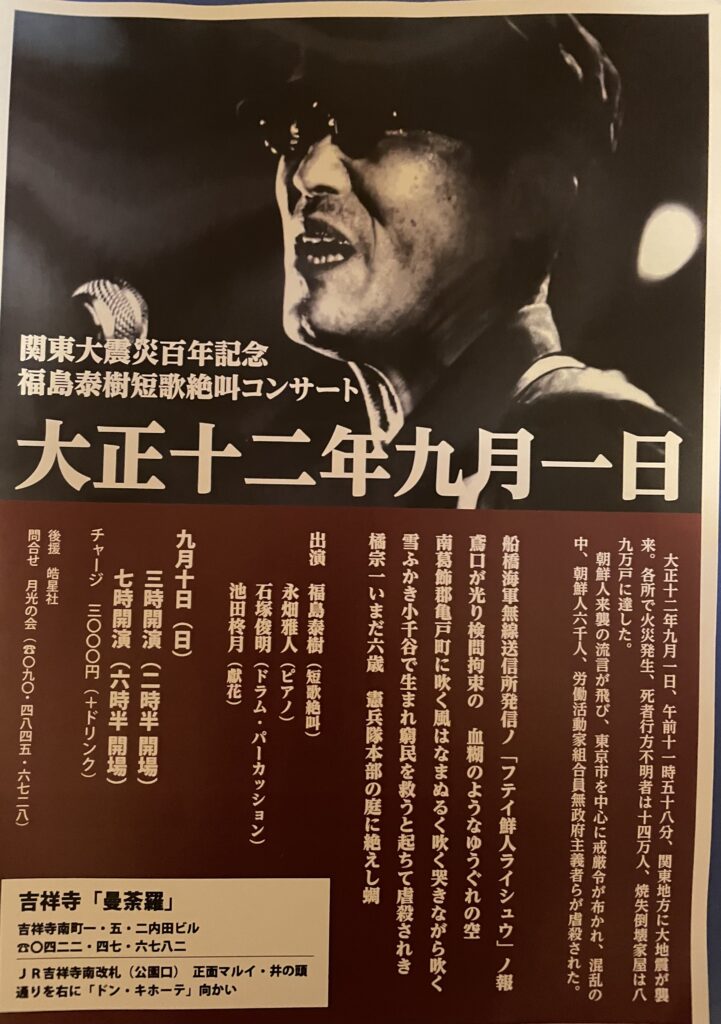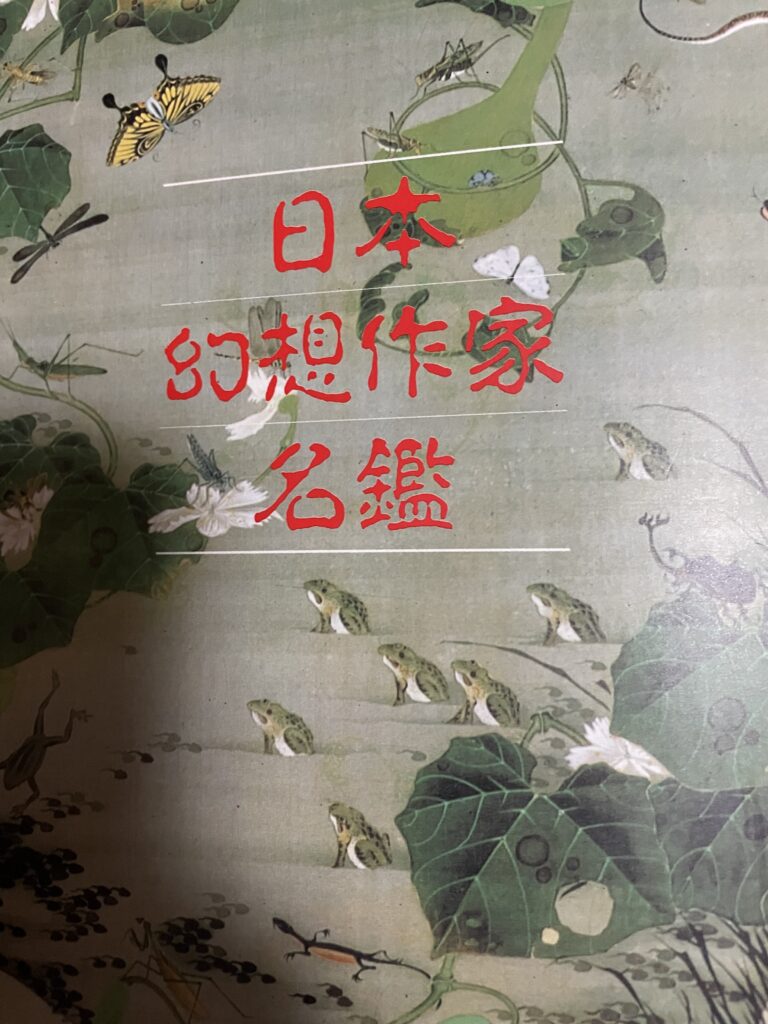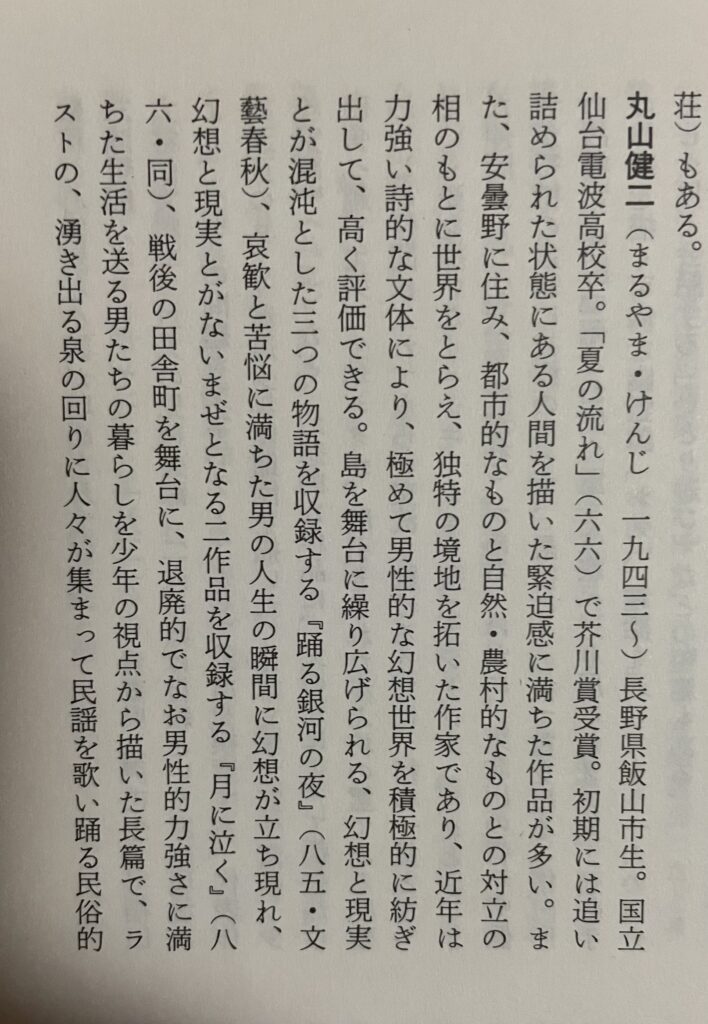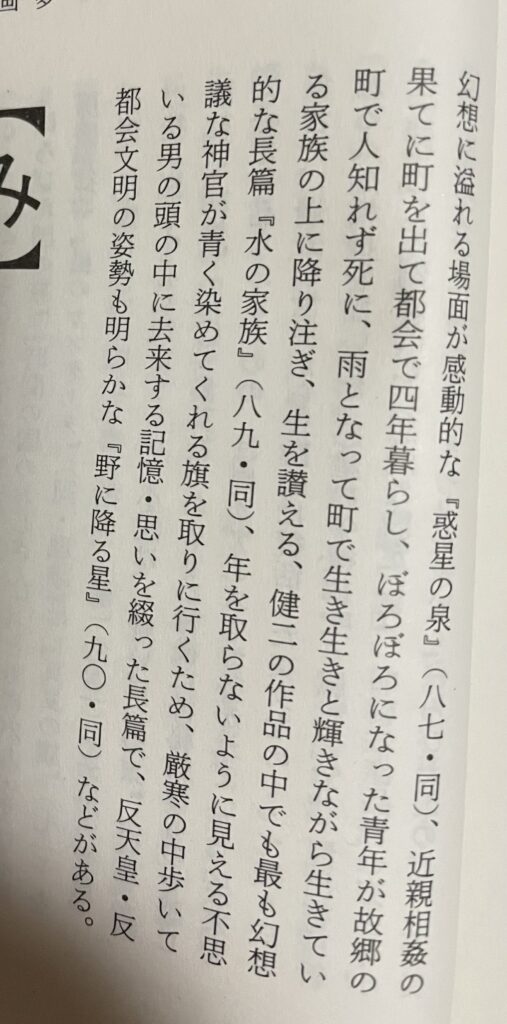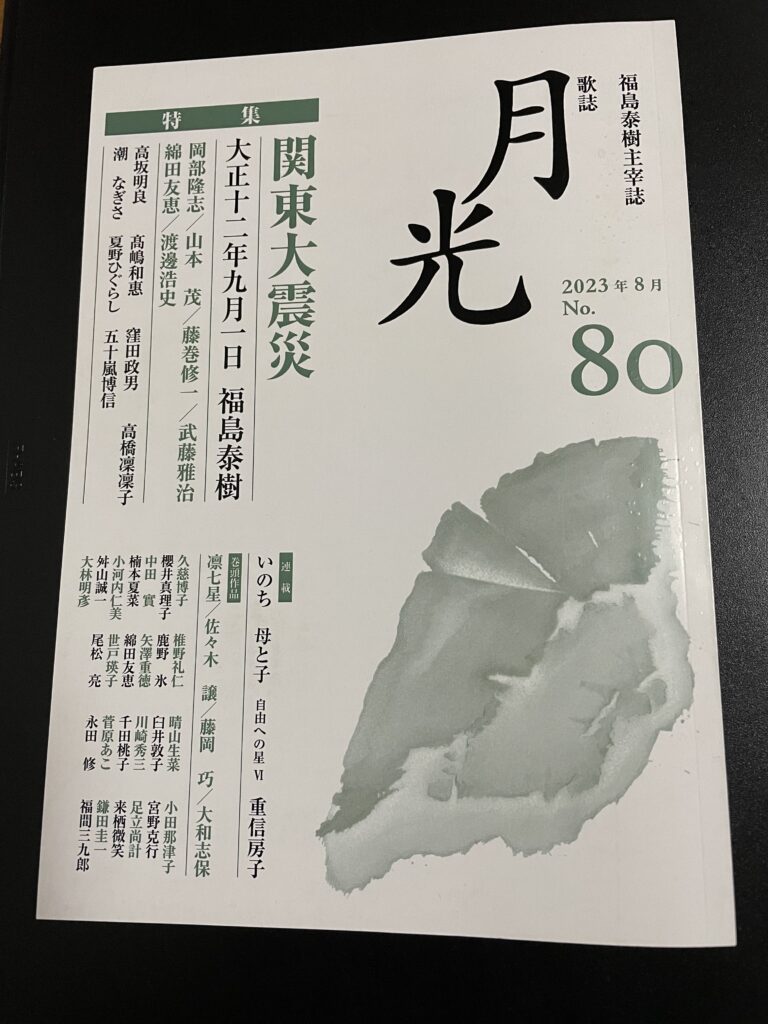丸山健二「夢の夜から 口笛の朝まで」より『今宵、観月の宴に』を読む
ー戦争への怒りみなぎる満月の夜の美しい幽霊譚ー

美しくも悲しく、戦争への怒りにあふれた月夜の幽霊幻想譚。
満月の夜に吊り橋「渡らず橋」が見た入水自殺した筈の老婆。
老婆は吊り橋の中央で花茣蓙を広げ、卓袱台を設え、三段の重箱に酒、薄を用意する。
そして歌いはじめると不思議!老婆は若やいだ娘の姿に変わり、「渡らず橋」は意識が朦朧としてくる……。
そんな不思議が言葉を尽くして語られると、眼前にリアルに見えてくるから言葉の力はすごい!と思う。
身に着けているものはなんら変わりはなくても、
その中身たるや、
なんと、
混濁の気配すらもない、
長い遍歴を経てきた生命の系譜にきっちりと則った、
陽気な暮らしや方正な美徳が最も似合いそうな、
ほっそりとした首にうっすらと流汗が認められる、
溌剌として初々しい、
忍従とはいっさい無縁な、
しとやかこのうえない娘盛りだったのだ。
動かしがたい過去数十年を一挙に圧縮してしまうという、
現世を司る理法を根底から分裂させる、
だからといって破壊的な激烈さをまったく感じさせぬ、
とほうもない瞬間をかいま見せられた仰天のなかにあって、
「渡らず橋」の動転はなおもつづき、
(丸山健二「夢の夜から 口笛の朝まで」より『今宵、観月の宴に』239頁)
やがて対岸に現れたのは血だらけの戦闘服を着た兵卒の姿。
老婆の双子の兄だった。とっくの昔に戦死している筈。
兄を戦争へと追い込んだ社会を作者・丸山健二は怒りを込めて書く。
森の美しさ、歌っているうちに若い娘へと変わる老婆の幻想を書いた後なので、この直球の怒りがなおさらズシンと響いてくる。
心貧しくて理不尽な、
富者による支配体制の永続的維持や、
個人を解体して家畜化することのみが眼目の国家権力の病的な欲望と、
ひたすら拝跪するしかない牽強としての現人神と、
国体の護持に欠かせぬ兵役という冷血なる従属関係と、
国家的英雄になれるかもしれないという危険な誘惑と、
(丸山健二「夢の夜から 口笛の朝まで」より『今宵、観月の宴に』243頁)
兄の惨めな戦死を書く言葉の隅々にまで静かな怒りがたぎっている。
侵略戦争という狂気の沙汰の最中、
縁もゆかりもない外地でまったく風味を欠いた日々を送り、
突撃一点張りの愚かで稚拙な作戦の犠牲者として貴重な生を閉じ、
命を剥奪された上に魂の放棄まで余儀なくされたまま、
荒涼たる戦場に打ち捨てられた存在としての長日月を耐え忍んだ実の兄を、
(丸山健二「夢の夜から 口笛の朝まで」より『今宵、観月の宴に』247頁)
幽霊となっても、戦争で犯した罪のため渡らず橋を渡ることができず、途中までしか進めない兄をこう語る。
図らずも国家的な悪行に手を染め、
大々的な暴力の集積たる戦争に加担し、
取り返しのつかぬ大罪を身に纏うことになった付けとしての、
犯してしまった誤りのあまりにおぞましい思い出をしこたま抱えて橋を渡り切るだけの力は残っておらず、
(丸山健二「夢の夜から 口笛の朝まで」より『今宵、観月の宴に』250頁)
だが満月の奇跡が!
二人は時を遡り、幼い少年少女に変わってゆく。
激しい怒りのあとで、心静かになる風景である。
そのとたん、
兄のほうもまたすかさず少年時代へと立ちもどり、
敵国も、
敵兵の殺害も、
戦場における不平等な死も、
まったく想像したことさえない、
ただ生きているだけで嬉しい、
天真爛漫な里山の童子と化し、
(丸山健二「夢の夜から 口笛の朝まで」より『今宵、観月の宴に』258頁)
あどけない童子となった兄と妹の姿に、これまでの怒りが薄らいでゆく。
でも戦争で亡くなったすべての方に、こうした幼い時期があった……と思うと、再び怒りと哀しみが押し寄せてくる。
やがて兄妹の幽霊は消え、森にはキツネやコノハズクの声が谺する………
谷川を見つめる吊り橋「渡らず橋」は、時を自由に行き来できる存在なのかもしれない。
幻想譚と戦争への強い怒りが一体となった魅力的な作品である。