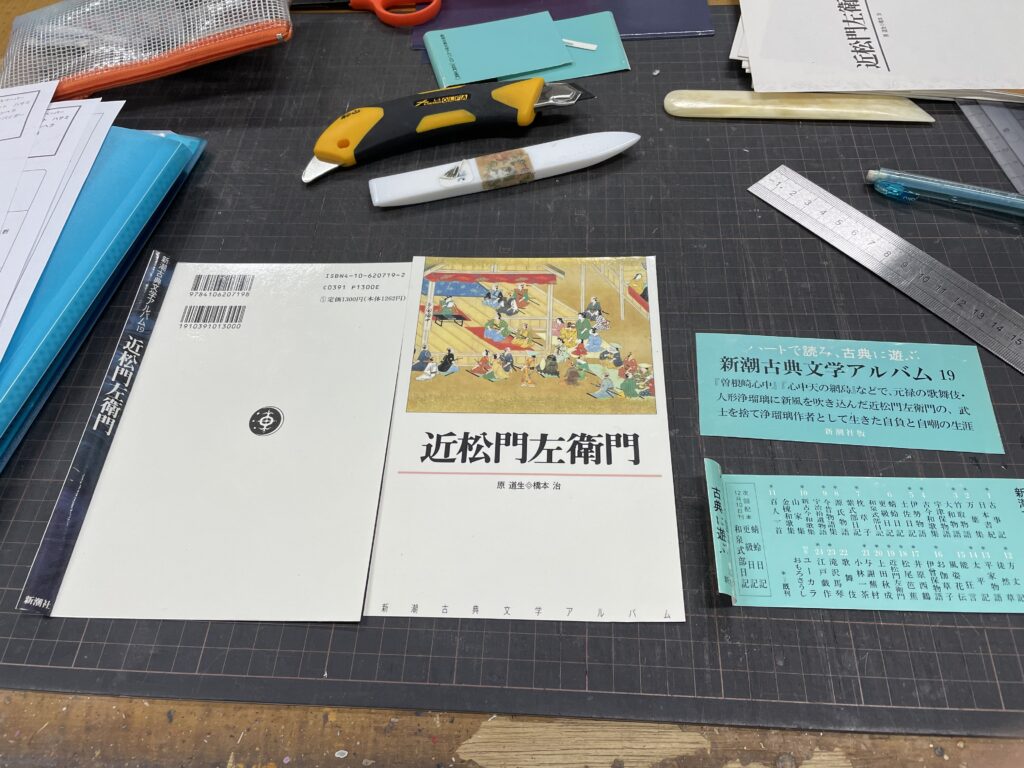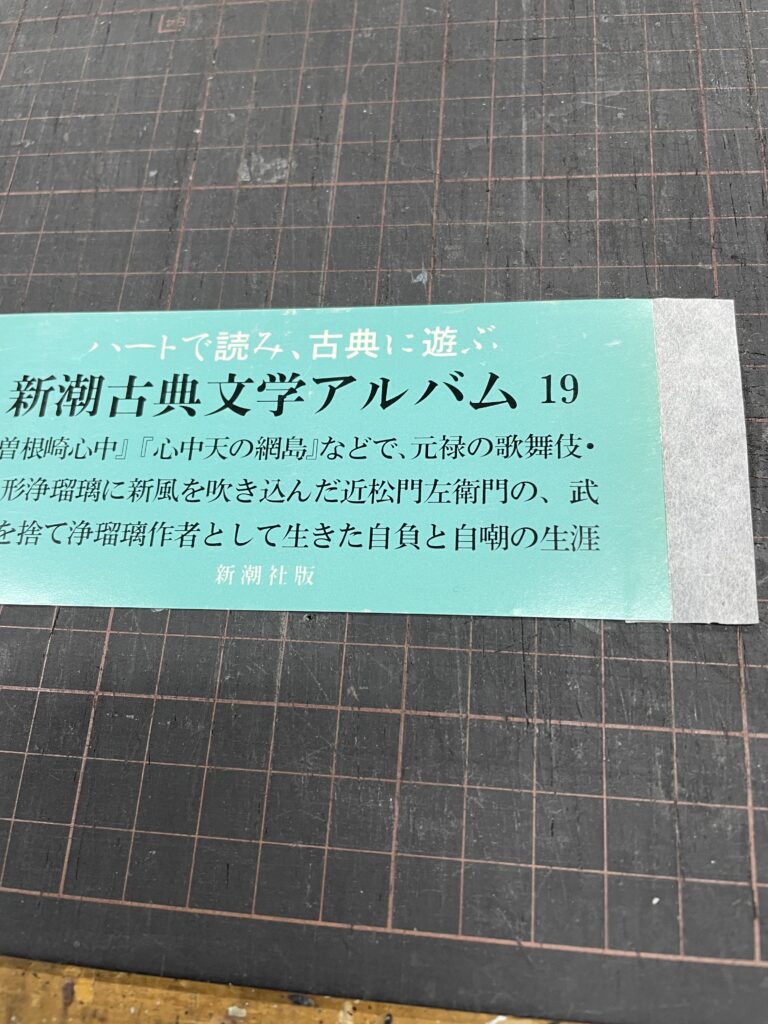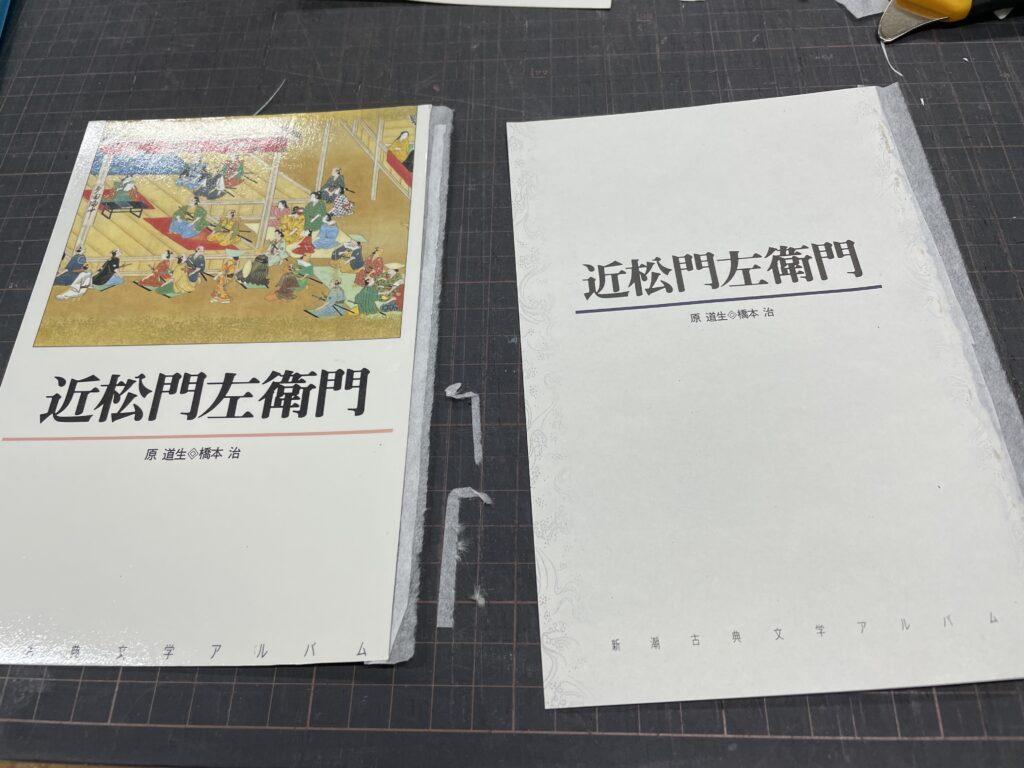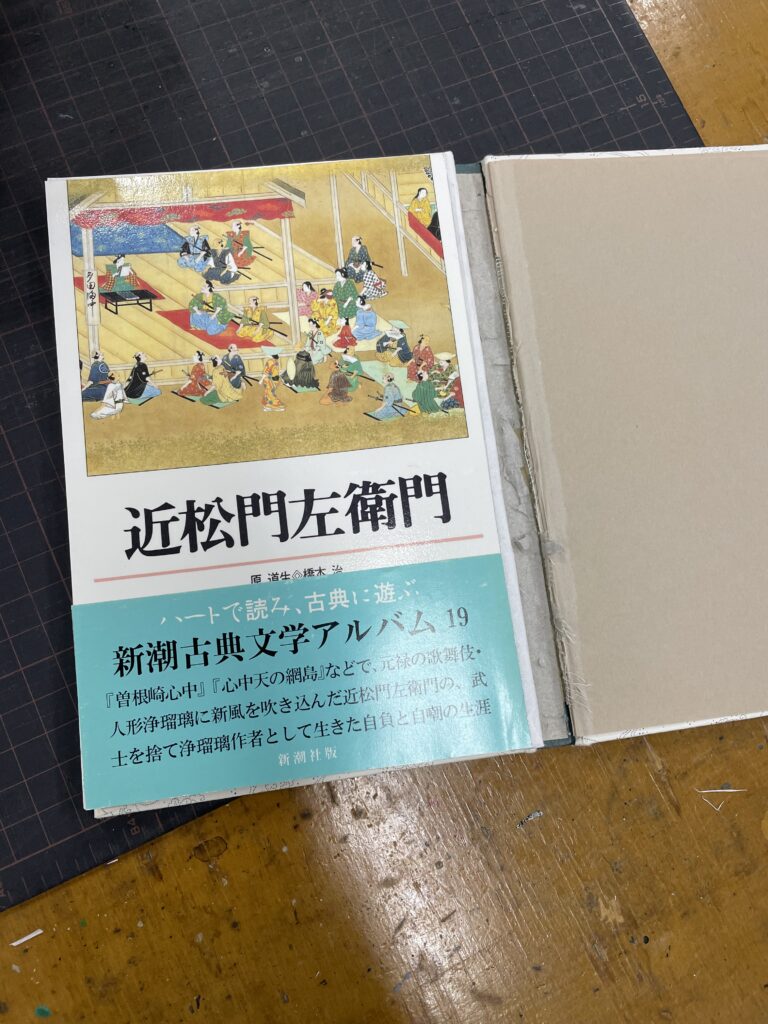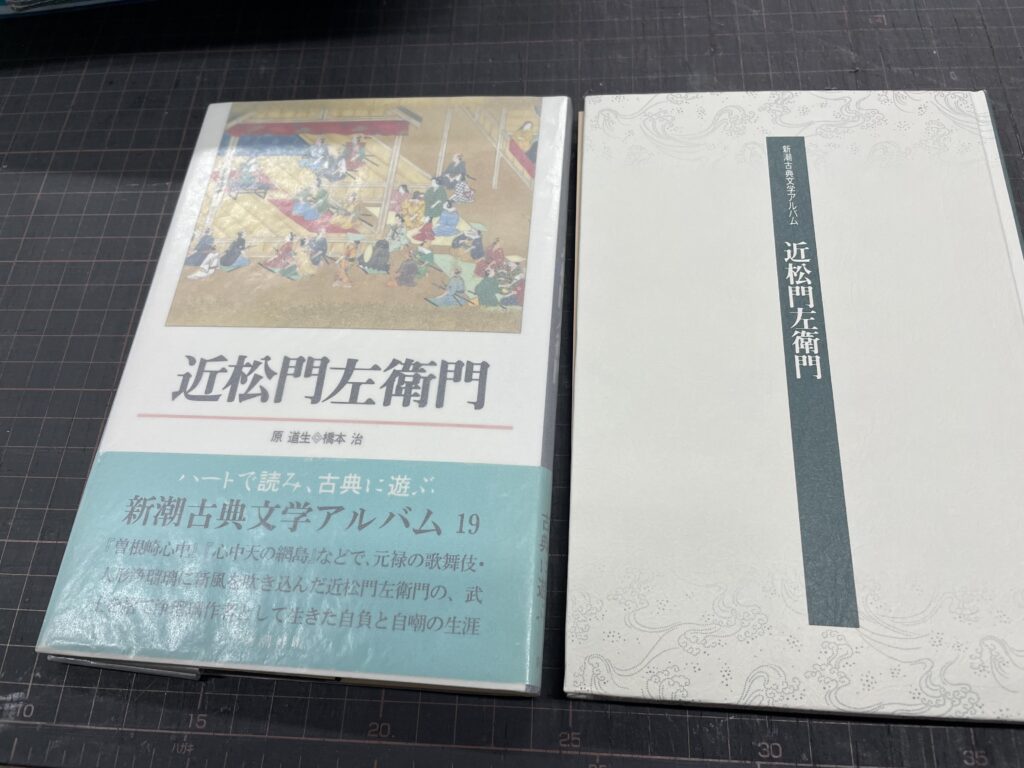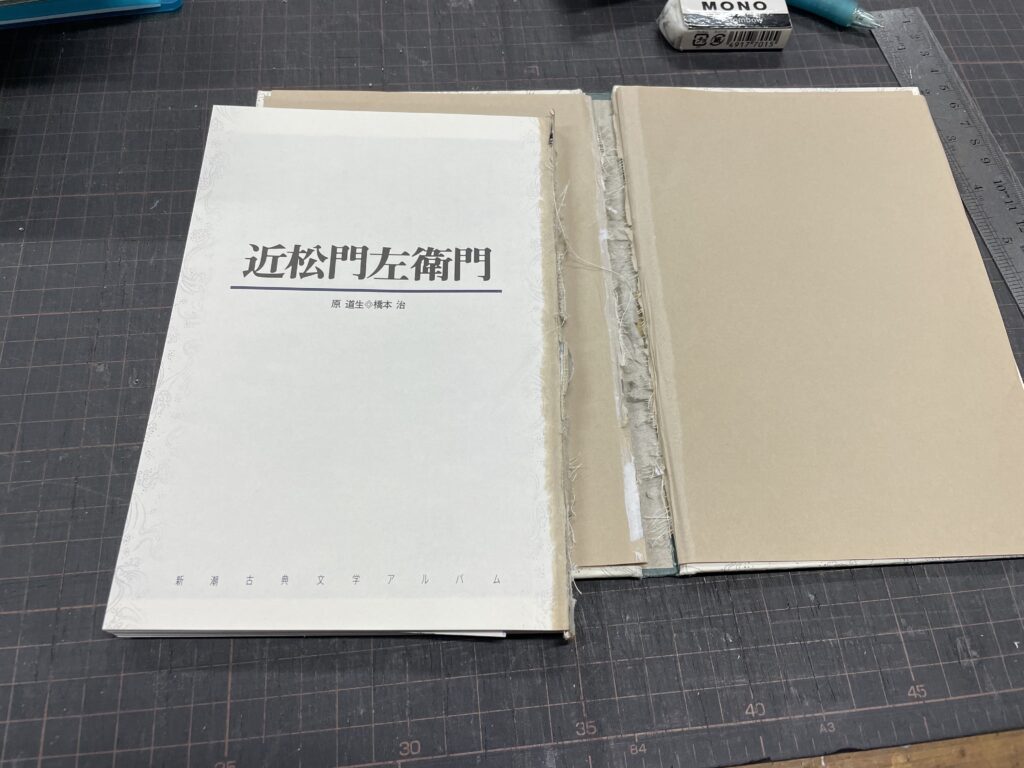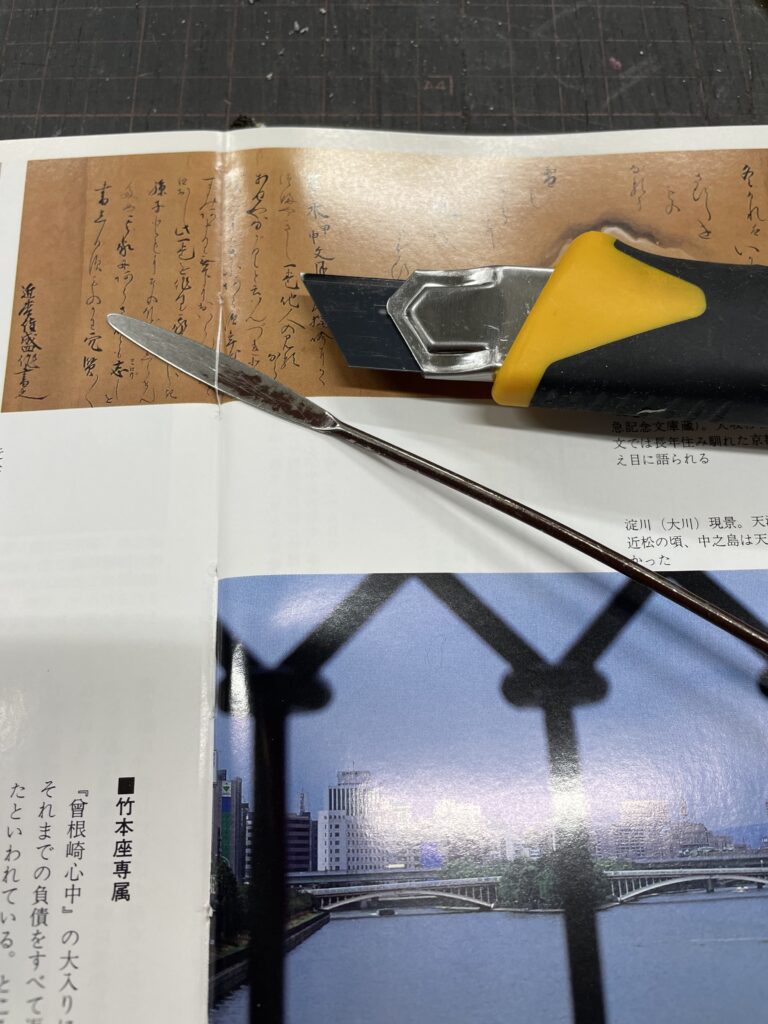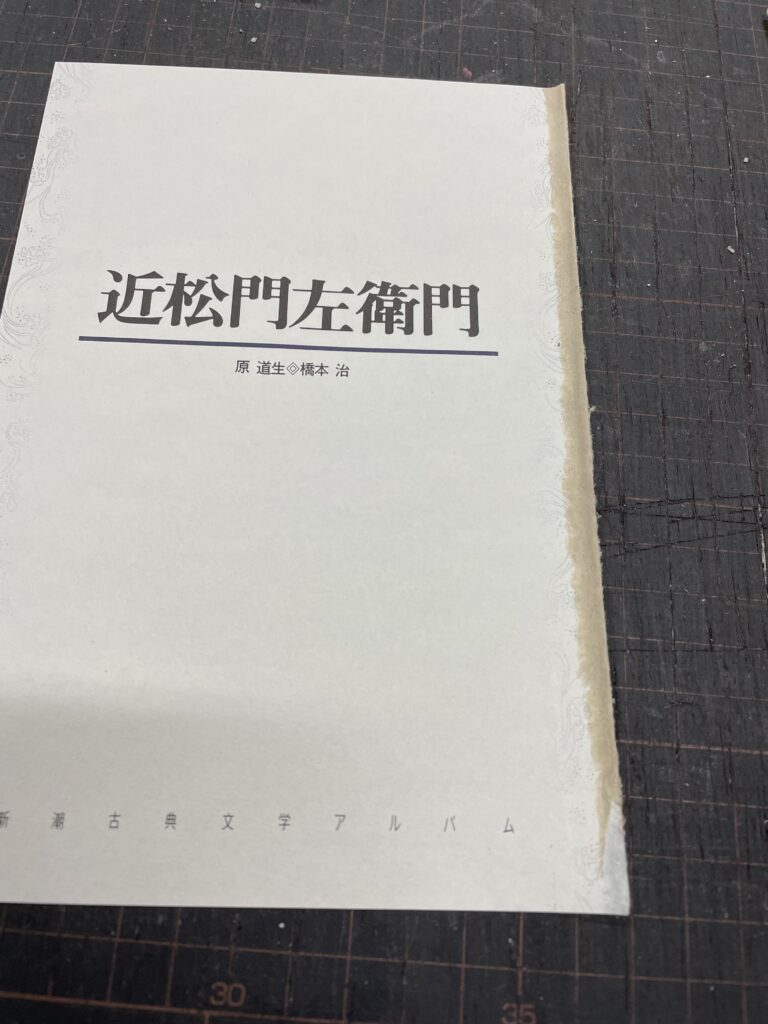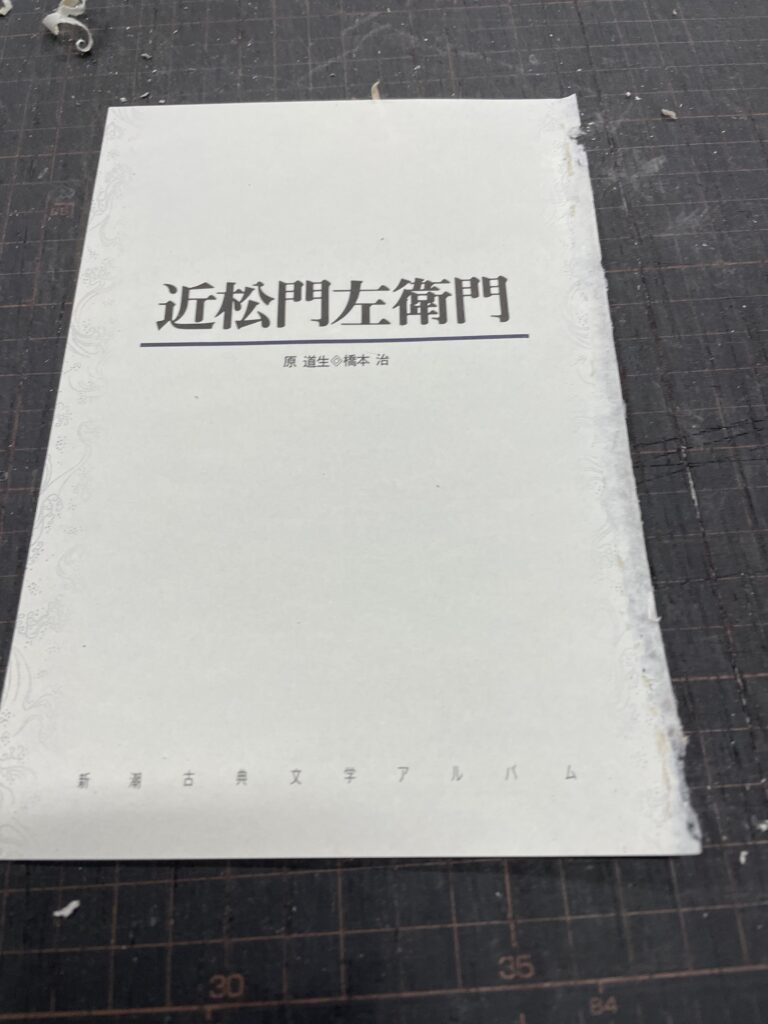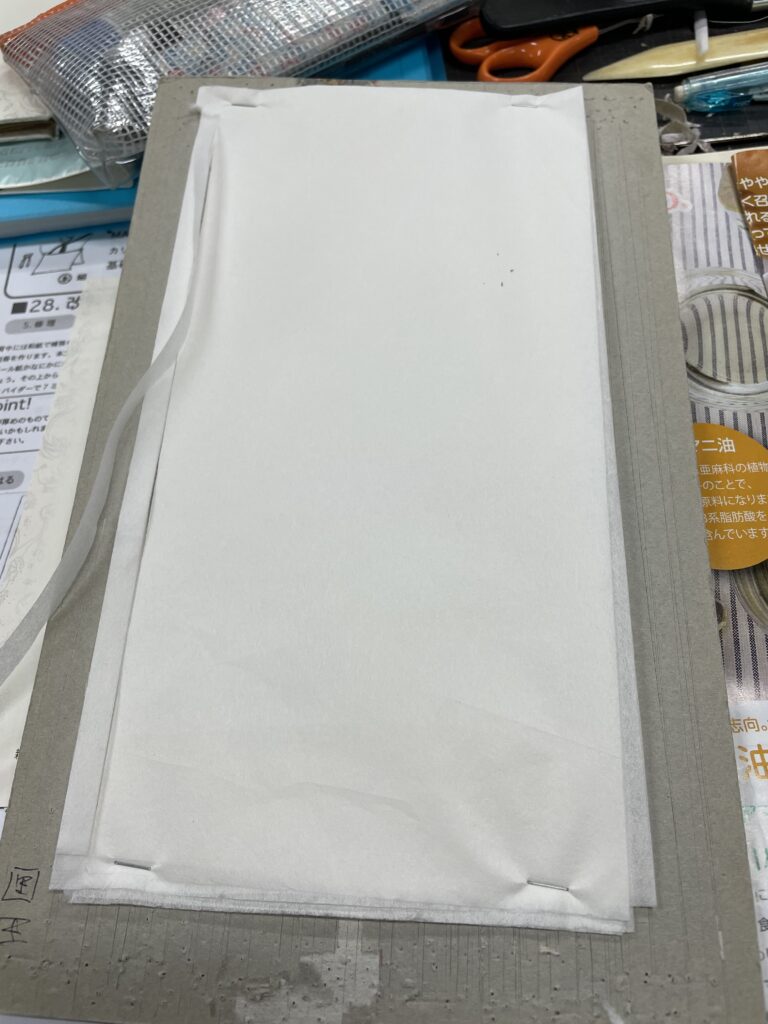変わりゆく日本語の風景 「たも」
文楽は、太夫さんが江戸時代の上方の言葉のまま、当時のアクセントのままで語る。
そんな文楽を観ていると、日本語が三百年ばかりの間になんて変わったことかと吃驚する。英語と比べるとエライ変化である。
可愛らしい娘さんの「私」にあたる言葉が「おれ」だったり、「わし」だったり。
浄瑠璃は五、七がベースなので、「この言葉が現代に残っていたなら、短歌をつくるときにいいのに」と思うことも度々。
そんな言葉の一つが「〜たも」である。
日本国語大辞典には、動詞に「て」のついた形について、補助動詞として用いる。……て下さい。……ておくれ。とある。
文楽には「いふてたも」「見せてたも」がしょっちゅう使われる気がする。
これを「言ってください」「見せておくれ」としたら、字数が多くなるし、元の「たも」の雰囲気が無くなる気がする。
「たも」には、人を悪の道へと唆すような小悪魔感がある気がする。
以下の文は、公金に手をつけた男が遊女に廓からの逃亡を迫る箇所。
「とんでたもやと」に変わる現代語はない気がしてならない。
それにしても「地獄の上の一足飛び」といい、「飛んでたもや」といい、恐るべきパワフルフレーズである。
せんぎに来るは今のこと、ぢごくの上の一そくとび、とんでたもやとばかりにてすがり
(近松門左衛門 冥途の飛脚)