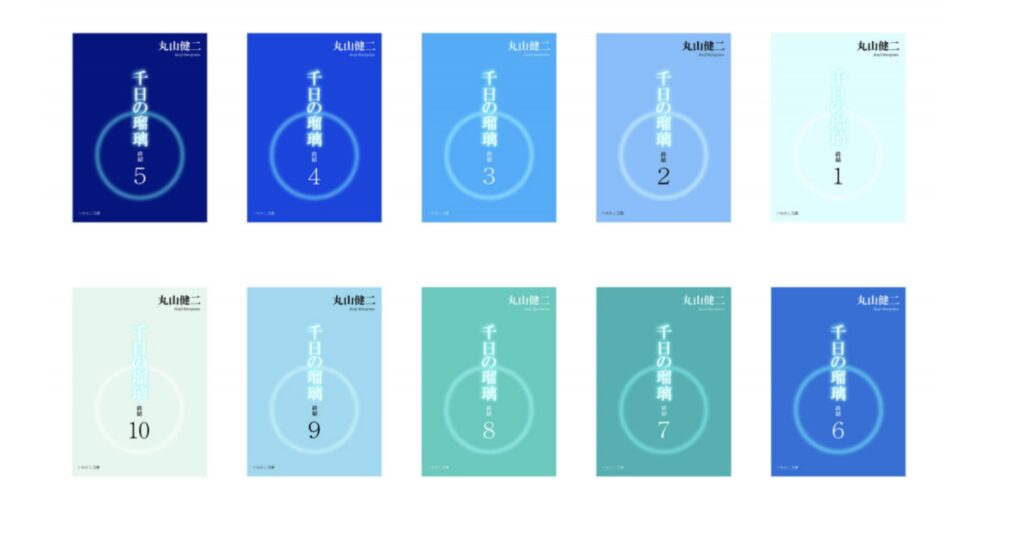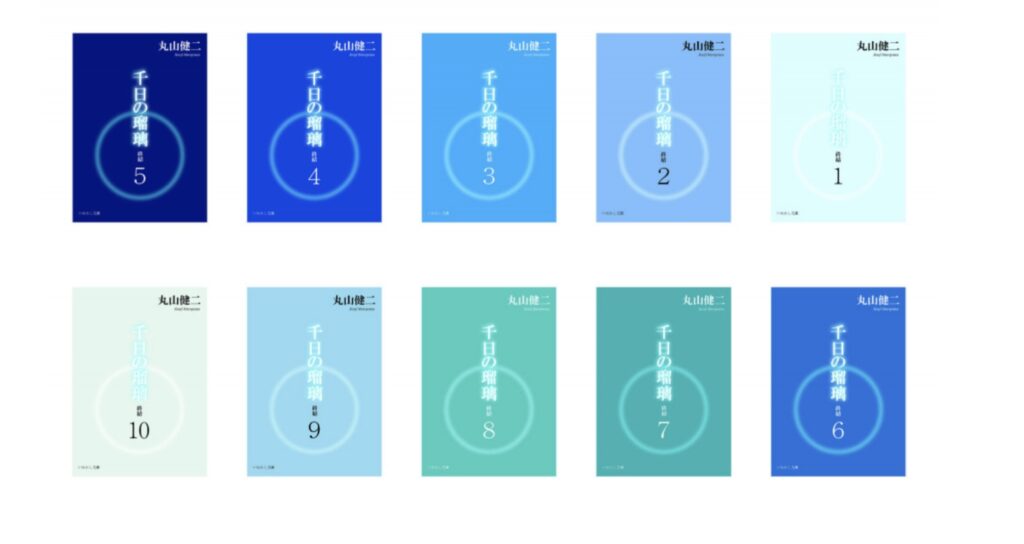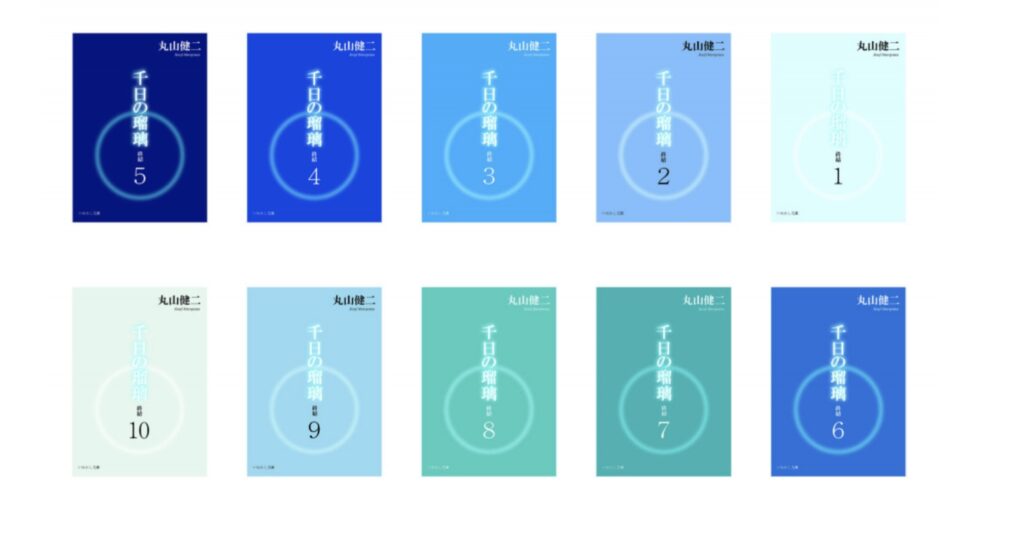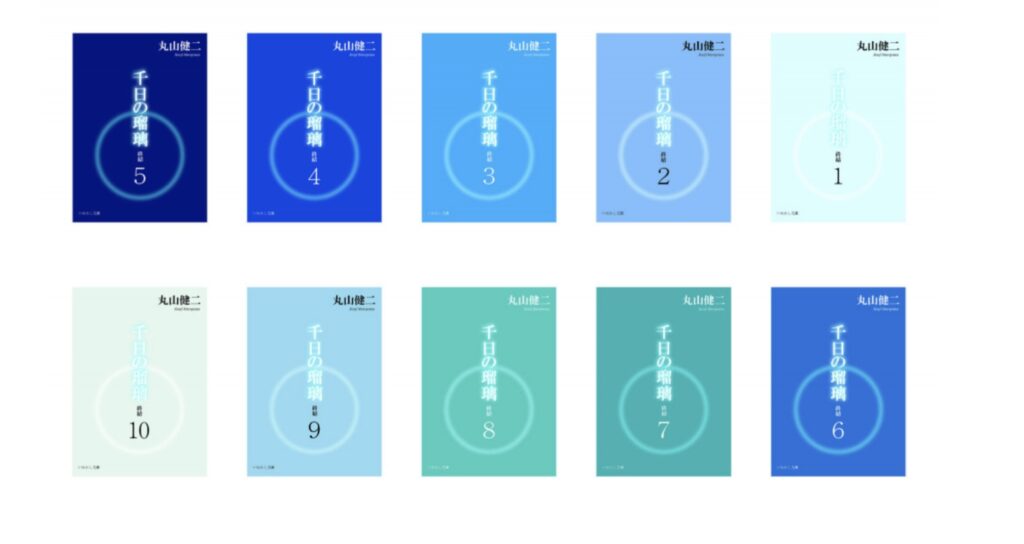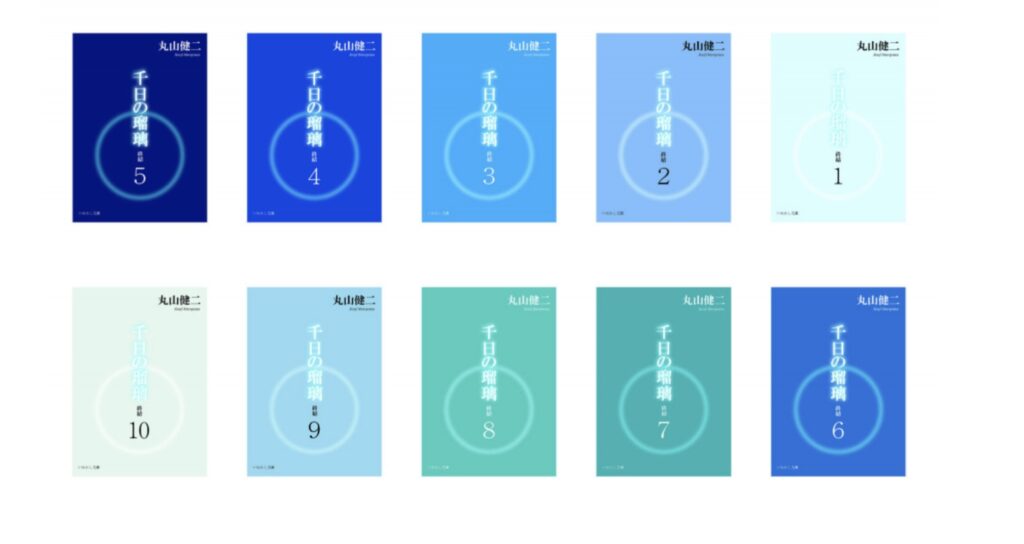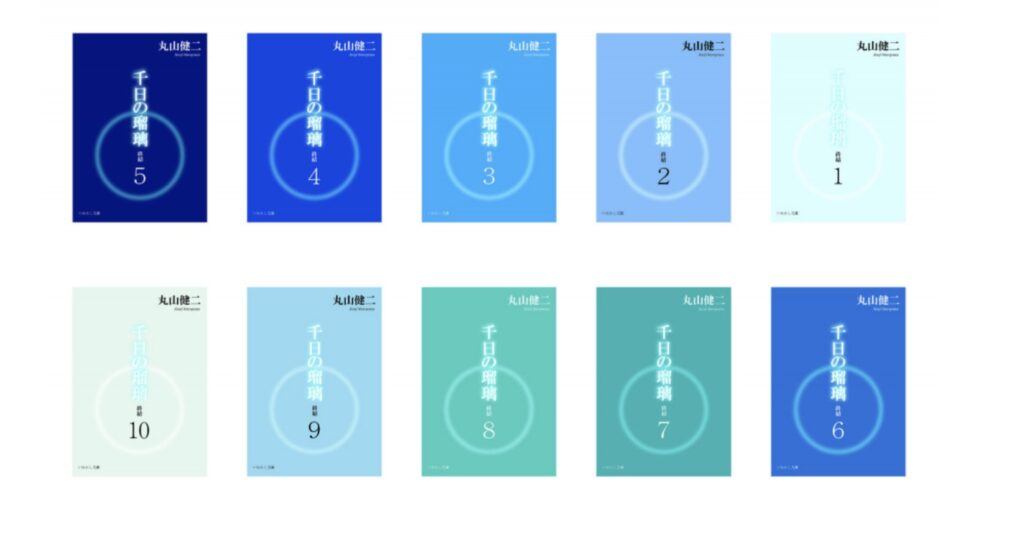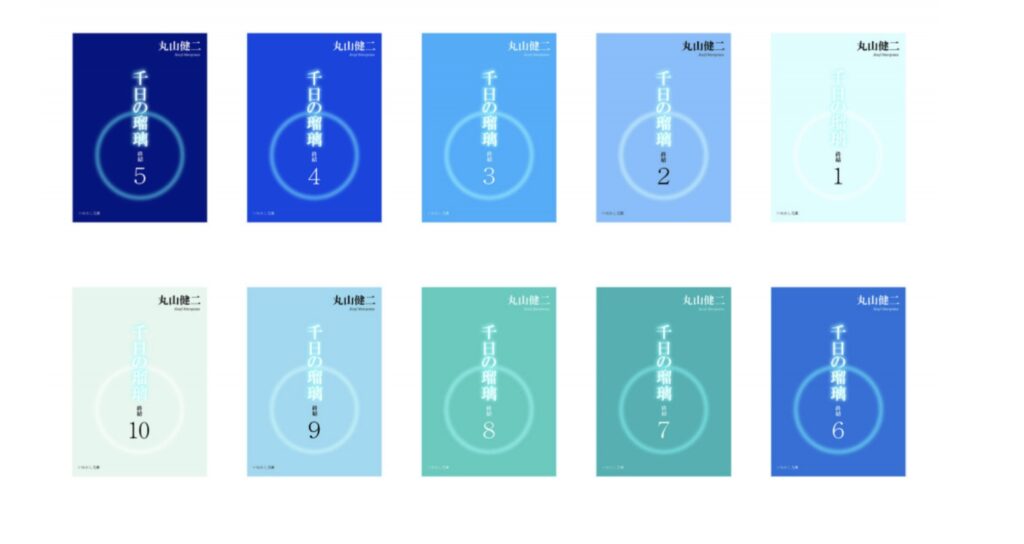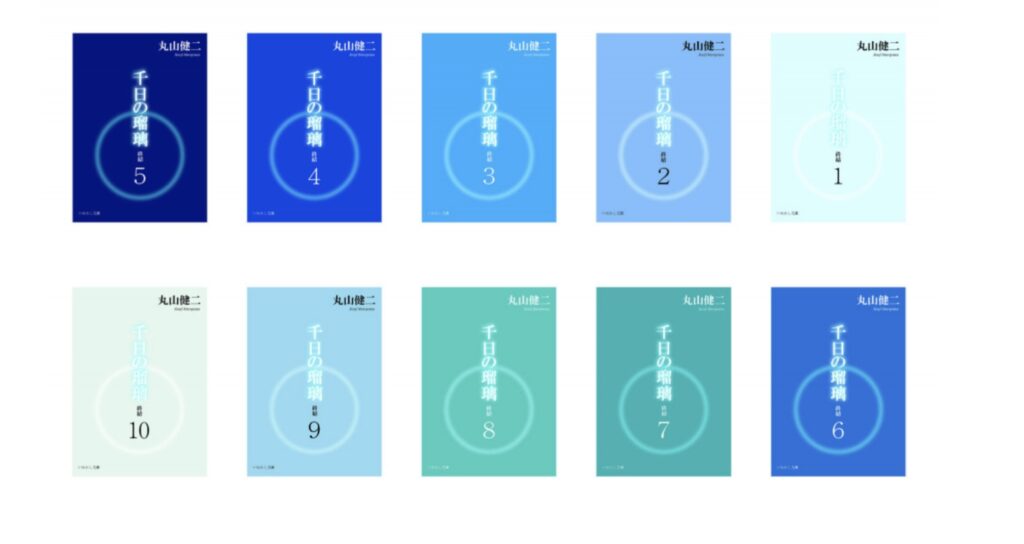丸山健二『千日の瑠璃 終結3』七月十六日を読む
ー「夏」が語る戦後日本ー

七月十六日は「私は夏だ」で始まる。
敗戦時に責任をうやむやにして問うべき責任をきっちり問わず、曖昧なままスタートした日本の戦後がいよいよ崩壊しかけているような昨今、思わず目にとまった文である。ただ「屈辱」と言うよりは、「愚かさ」やら「身の錆」やらの方が、私の心情的にはしっくりくる気がする。
そして私は
無条件降伏という屈辱を戦勝国に押しつけられたせいで
今もって民主主義のなんたるかを理解していない
身の程知らずのこの小国を、
永久に振り捨てられそうにない
島国根性と共に
すっぽりと覆う。
(丸山健二『千日の瑠璃 終結3』